5.2 南海地震〜東南海地震〜想定東海地震のモデル化に関する検討
5.2.1 目的
西日本の確率論的地震動予測地図の試作版を作成する際の地震活動のモデルのうち、南海〜東南海〜想定東海地震のモデル化については2.3.2(1)に示されている。ただし、モデル化の審議過程では他の複数のモデル化案が検討の対象とされた。最終的には採用に至らなかったが、検討対象とされたモデル化案について以下に示す。
5.2.2 検討対象とされたモデル化案の概要
ここで対象としている地震名と図5.2.2-1に示した震源域との対応は次のとおりである。また、過去の地震の震源域との対応を表5.2.2-1に示す。(地震調査委員会,2001、中央防災会議「東海地震に関する専門調査会」,2001)
以下では、検討対象とされた地震活動モデルのうち、最終的に採用されたもの(2.3.2(1)参照)を除く4つのモデル化案を示す。
4つのモデル化案の骨子を以下に要約する。なお、最終的に採用されたモデルは下記の案1に類似しており、複数の地震が連動して発生する確率の取り扱いが異なるものである。
- ○案1
- 3つの地震は経時的にそれぞれ独立な別個の更新過程に従う。
- 時間原点は南海地震=1946年、東南海地震=1944年、想定東海地震=1854年。
- 対象期間内に複数の地震が発生する場合には、予め設定した確率で複数の地震が連動して発生するケースを考慮する。連動のパターンは、南海地震+東南海地震、東南海地震+想定東海地震、南海地震+東南海地震+想定東海地震の3種類。
- 各地震が経時的に独立に発生するという仮定の是非(南海と想定東海が発生し東南海は発生しないパターンもあり得る)、ならびに「想定東海地震が今後10年程度発生しなかった場合にはもはや単独では発生しない」という仮説を取り入れられない(発生確率は時間経過とともにどんどん大きくなる)点が問題点として指摘できる。
- ○案2
- 東南海地震と想定東海地震は経時的にそれぞれ独立な別個の更新過程に従う。
- 南海地震は東南海地震の発生に付随して発生するとし、その発生確率は長期評価の確率値を参考として独自に付与する。ここで東南海地震が発生しない場合には南海地震は発生しないことに注意が必要である。
- 時間原点は、東南海地震=1944年、想定東海地震=1854年。
- 対象期間内に複数の地震が発生する場合には、予め設定した確率で複数の地震が連動して発生するケースを考慮する。連動のパターンは、南海地震+東南海地震、東南海地震+想定東海地震、南海地震+東南海地震+想定東海地震の3種類。
- 南海地震が東南海地震に付随して発生するという仮定の是非、南海地震の発生確率(東南海地震が発生したという条件下での条件付確率)の設定根拠、ならびに「想定東海地震が今後10年程度発生しなかった場合にはもはや単独では発生しない」という仮説を取り入れられない(発生確率は時間経過とともにどんどん大きくなる)点が問題点として指摘できる。
- ○案3
- 南海地震〜東南海地震は経時的には単一の更新過程に従う。時間原点は東南海地震の1944年。
- 想定東海地震は南海地震〜東南海地震の更新過程の系列とは全く別個に独立に発生するとし、発生確率は独自に付与する。(本資料では、30年、50年ともに50%と仮定=今後10年間は南海地震、東南海地震より高いが、10年程度で頭打ちとなると仮定)
- 南海地震〜東南海地震の震源域は、各領域が単独で震源域となる場合と複数の領域が連動して震源域となる場合をケース分けし、それぞれのケースが予め設定された確率で生起する。ここで、東南海地震は予め設定した確率で想定東海地震の領域Zまで震源域が及ぶ可能性も考慮する。
- 南海地震〜東南海地震を単一の時系列とすることの是非(長期評価では南海地震と東南海地震で別個の時系列としている)、ならびに想定東海地震を別の独立な地震とすることよって領域Zが2回震源域となる可能性を認めていることの是非(想定東海地震が安政東海地震の割れ残りとするなら2回震源域となってもよい?)が問題点として指摘できる。
- ○案4
- 南海地震〜東南海地震は経時的には単一の更新過程に従う。時間原点は東南海地震の1944年。
- 想定東海地震は上記の更新過程の系列とは別個に発生するが、南海地震〜東南海地震と独立ではない。南海地震〜東南海地震と想定東海地震のいずれが先に発生するかで、その後のシナリオを変える。想定東海地震が先に発生した場合には、次の南海地震〜東南海地震では震源域は想定東海地震の領域Zにまでは及ばないと仮定する。また、南海地震〜東南海地震が先に発生した場合には想定東海地震はもはや発生しないと仮定する。
- 南海地震〜東南海地震の震源域は、各領域が単独で震源域となる場合と複数の領域が連動して震源域となる場合をケース分けし、それぞれのケースが予め設定された確率で生起する。ここで、東南海地震は、想定東海地震よりも先に発生する場合に限って、予め設定した確率で想定東海地震の領域Zまで震源域が及ぶ可能性も考慮する。
- 各地震の発生の有無と発生の順序を考慮したイベントツリーを作成し、それぞれのイベントが予め設定した確率で発生する。想定東海地震の発生確率は独自に付与する。(本資料では、30年、50年ともに50%と仮定=今後10年間は南海地震、東南海地震より高いが、10年程度で頭打ちとなると仮定)
- 南海地震〜東南海地震を単一の時系列とすることの是非(長期評価では南海地震と東南海地震で別個の時系列としている)の問題、また想定東海地震と南海〜東南海地震との相関性(発生順序に応じて相手方の地震の発生確率や震源域が変わる)を仮定しているが、「実例がない状況においてそのシナリオが断定的すぎないか?」という問題点が指摘できる。
4つのモデル化案の比較を図5.2.2-2に示す。各案とも図の上半分が時系列のイメージで、下向きの矢印が更新過程を表わしている。図の下半分は震源域(連動)のパターンとその生起確率である。
案1、2と案3、4の考え方の違いとして、個々の震源域の時系列を基本としてそれに複数の震源域の連動を考えるか(案1、2)、あるいは全体の時系列を基本としてそれに想定東海地震を別に考えるか(案3、4)が指摘できる。それに付随して、想定東海地震を独自の更新過程(1854年が時間原点)とするか(案1、2)、時間的にまったく別に発生するか(案3、4)が異なっている。
震源域の生起確率を設定するに際しての共通の論点として、1498年の明応の地震では南海地震は発生しなかったのかどうか?、1605年の慶長の地震は1707年の宝永の地震と同じパターンと考えてよいのかどうか?、がある。
5.2.3 検討対象とされたモデル化案
A. モデル化案1
- 前提条件
- 「南海トラフの地震の長期評価について」において、南海地震と東南海地震は前回活動時期および活動間隔(前回の地震から次の地震までの標準的な発生間隔)ともに別の値が提示されている。
- 想定東海地震は南海地震〜東南海地震の時系列とは別個に単独で発生する可能性がある。
- 時系列のモデル化
- 南海地震、東南海地震、想定東海地震は経時的にそれぞれ「独立に別個の更新過程」に従って発生すると仮定する。
- 各地震の発生確率算定用のパラメータは長期評価に基づき表5.2.3-1のように設定する。
- 以上の条件で、西暦2004年1月から30年間、50年間の各地震の発生確率は表5.2.3-2のようになる。
(注:各地震ともに50年程度では2回発生する確率はほぼ0である)
- 震源域のモデル化
- 震源域については各地震が単独に発生するか、あるいは複数の地震が連動して発生すると仮定する。各地震の震源域はそれぞれの領域内で予め設定されたモデルとし、モデルの一部が震源域となる場合は想定しない。
- 複数の地震の連動については次の仮定を設ける。
- 3つの地震が対象期間内にすべて発生する場合に、
南海〜東南海〜想定東海の連動の確率:2/3(慶長、宝永)
南海〜東南海の連動の確率:0(事例なし)
東南海〜想定東海の連動の確率:1/3 (安政)
それぞれが単独で発生する確率:0 (事例なし)
- 東南海地震と想定東海地震が対象期間内にいずれも発生し、南海地震が発生しない場合に、
東南海〜想定東海の連動の確率:1(明応)
それぞれが単独で発生する確率:0(事例なし)
- 南海地震と東南海地震が対象期間内にいずれも発生し、想定東海地震が発生しない場合に、
南海〜東南海の連動の確率:0(事例なし)
それぞれが単独で発生する確率:1(昭和南海〜東南海)
(注)過去の地震の震源域を次のように推定した。
明応(1498年)=東南海+想定東海の一部(連動)
慶長(1605年)=南海+東南海+想定東海の一部(連動)
宝永(1707年)=南海+東南海+想定東海(連動)
安政(1854年)=東南海+想定東海(連動)/南海(単独)
昭和(1944、1946年)=東南海(単独)/南海(単独)
- なお、西日本の確率論的地震動予測地図(試作版)で採用された地震活動モデル(2.3.2(1)参照)は、モデル化案1のうち、上述の複数地震の連動確率が異なる(各ケースとも均等な確率を付与)ものとなっている。
- 連動を考慮した各地震の発生確率と地震ハザードの計算方法
- 以上の条件の下で、各地震が発生する確率は表5.2.3-3のようになる。
- 各ケースは排反かつすべての場合を尽くしているので、地震ハザードの計算は各ケースの生起確率と当該ケースに対する地震動強さの超過確率を下記13ケースについて積和することにより求められる。
- 問題点
- 南海地震と東南海地震のモデルは長期評価を踏襲している。しかし、各地震が経時的に独立に発生するという仮定は、地震学的な観点から違和感がある。(南海と想定東海が発生し、東南海は発生しないというパターンもあり得る。)
- 「想定東海地震が安政東海地震の割れ残り」とするなら、1854年を時間原点とした発生確率は根拠がある。ただし、「想定東海地震が今後10年程度発生しなかった場合にはもはや単独では発生しない」という仮説は取り入れられない。
B. モデル化案2
- 前提条件
- 「南海トラフの地震の長期評価について」において、南海地震と東南海地震は前回活動時期および活動間隔(前回の地震から次の地震までの標準的な発生間隔)ともに別の値が提示されているが、歴史的に南海地震と東南海地震は同時(連動)あるいは非常に近接した時期に発生している。
- 想定東海地震は南海地震〜東南海地震の時系列とは別個に単独で発生する可能性がある。
- 時系列のモデル化
- 東南海地震と想定東海地震は経時的にそれぞれ「独立に別個の更新過程」に従って発生すると仮定する。
- 南海地震は東南海地震の発生に付随して発生するとし、その発生確率は長期評価の確率値を参考として独自に付与する。ここで、東南海地震が発生しない場合には南海地震は発生しない(南海地震が発生し東南海地震が発生しないケースはあり得ない)ことに注意が必要である。
- 各地震の発生確率算定用のパラメータは長期評価に基づき表5.2.3-4のように設定する。
- 以上の条件で、西暦2004年1月から30年間、50年間の各地震の発生確率は表5.2.3-5のようになる。
(注:各地震ともに50年程度では2回発生する確率はほぼ0である)
- 一方、南海地震の発生確率(東南海地震が発生したという条件下での条件付確率)は長期評価を基に算定される発生確率と東南海地震の発生確率より、表5.2.3-6のように定める。(30年:47%/58%を丸めて80%、50年:81%/88%を丸めて90%)
- 震源域のモデル化
- 震源域については各地震が単独に発生するか、あるいは複数の地震が連動して発生すると仮定する。各地震の震源域はそれぞれの領域内で予め設定されたモデルとし、モデルの一部が震源域となる場合は想定しない。
- 複数の地震の連動については次の仮定を設ける。
- 3つの地震が対象期間内にすべて発生する場合に、
南海〜東南海〜想定東海の連動の確率:2/3(慶長、宝永)
南海〜東南海の連動の確率:0(事例なし)
東南海〜想定東海の連動の確率:1/3 (安政)
それぞれが単独で発生する確率:0 (事例なし)
- 東南海地震と想定東海地震が対象期間内にいずれも発生し、南海地震が発生しない場合に、
東南海〜想定東海の連動の確率:1(明応)
それぞれが単独で発生する確率:0(事例なし)
- 南海地震と東南海地震が対象期間内にいずれも発生し、想定東海地震が発生しない場合に、
南海〜東南海の連動の確率:0(事例なし)
それぞれが単独で発生する確率:1(昭和南海〜東南海)
(注)過去の地震の震源域を次のように推定した。
明応(1498年)=東南海+想定東海の一部(連動)
慶長(1605年)=南海+東南海+想定東海の一部(連動)
宝永(1707年)=南海+東南海+想定東海(連動)
安政(1854年)=東南海+想定東海(連動)/南海(単独)
昭和(1944、1946年)=東南海(単独)/南海(単独)
- 連動を考慮した各地震の発生確率と地震ハザードの計算方法
- 以上の条件の下で、各地震が発生する確率は表5.2.3-7のようになる。
- 各ケースは排反かつすべての場合を尽くしているので、地震ハザードの計算は各ケースの生起確率と当該ケースに対する地震動強さの超過確率を下記11ケース(ケース2と7はあり得ない)について積和することにより求められる。
- 案1と案2の各ケースの生起確率の違いを表5.2.3-8に示す。
- 問題点
- 南海地震が東南海地震に付随して発生するという仮定の是非。また、南海地震の発生確率(東南海地震が発生したという条件下での条件付確率)は長期評価を参考として設定しているが、そもそも長期評価での南海地震の発生確率は東南海地震とは独立に評価されたものであり、東南海地震が発生したという条件下での条件付確率ではない。
- 「想定東海地震が安政東海地震の割れ残り」とするなら、1854年を時間原点とした発生確率は根拠がある。ただし、「想定東海地震が今後10年程度発生しなかった場合にはもはや単独では発生しない」という仮説は取り入れられない。
C. モデル化案3
- 前提条件
- 歴史的に、南海地震と東南海地震(想定東海地震の領域Zまでが震源域となる場合を含む)は同時(連動)あるいは非常に近接した時期に発生している。
- 想定東海地震は南海地震〜東南海地震の一連の時系列とは別個に単独で発生する可能性がある。
- 時系列のモデル化
- 南海地震と東南海地震(想定東海地震の領域Zまでが震源域となる場合を含む:以下、南海〜東南海地震と記す)は経時的に「単一の更新過程」に従う。
- 想定東海地震は上記の更新過程の系列とは別個に独立に発生するとし、発生確率は独自に付与する。
- 南海〜東南海地震の発生確率算定用のパラメータは、長期評価の東南海地震の値(表5.2.3-9)を用いる。
- 以上の条件で、西暦2004年1月から30年間、50年間の地震の発生確率は表5.2.3-10のようになる。
(注: 50年程度では2回発生する確率はほぼ0である)
- 一方、想定東海地震の発生確率は、「今後10年間は南海地震、東南海地震より高いが、10年程度で頭打ちとなる」という前提の下に、本資料では30年、50年ともに50%と仮置きしておく(表5.2.3-11)。
- 震源域のモデル化
- 南海〜東南海地震の震源域については各領域が別個に震源域となるか、あるいは複数の領域が連動して震源域となると仮定する。震源域はそれぞれの領域内で予め設定されたモデルとし、モデルの一部が震源域となる場合は想定しない。
- 南海〜東南海地震については過去の地震のパターンに基づき、明応、慶長、宝永、安政、昭和の5回のうちの2回(慶長、宝永)が3地震の連動(領域X+Y+Z)、2回(明応、安政)が南海地震と東南海地震&想定東海地震の連動(領域X、Y+Z)、1回(昭和)が南海地震と東南海地震が別個(領域X、Y)として各パターンの生起確率を与える。なお、明応の地震は南海地震の発生は確認されていないが、本案では南海地震〜東南海地震を単一の時系列としているために、東南海地震が発生し南海地震が発生しないパターンは考慮できない。したがって、ここでは明応も安政と同じパターンと仮定した。また、南海地震と東南海地震のみの連動(領域X+Y)は過去にはないので、このケースの生起確率は0としている。
- 一方、想定東海地震は領域Zが震源域となる。南海〜東南海地震と想定東海地震を別にモデル化するため、将来30年あるいは50年の間に領域Zが2回震源域となる可能性を認めていることになる。
- 地震ハザードの計算方法
- 以上の条件の下で南海〜東南海地震の地震ハザードの計算は次式のようになる。
- ここで、
 は将来 は将来  年間( 年間(  =30または50)での南海〜東南海地震の発生確率である。 =30または50)での南海〜東南海地震の発生確率である。
- また、
 は南海〜東南海地震が発生した場合に、対象地点で地震動強さYが少なくとも1度以上 は南海〜東南海地震が発生した場合に、対象地点で地震動強さYが少なくとも1度以上
 を超える確率で、上述した震源域のパターンとなる生起確率 を超える確率で、上述した震源域のパターンとなる生起確率  (表5.2.3-12)と、その震源域の地震に対する地震動強さYの超過確率 (表5.2.3-12)と、その震源域の地震に対する地震動強さYの超過確率 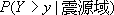 を用いて、表5.2.3-12最右欄の4ケースの確率の和として算定できる。 を用いて、表5.2.3-12最右欄の4ケースの確率の和として算定できる。
- なお、トータルのハザードには、上記の南海〜東南海地震によるハザードの他に、想定東海地震によるハザードが加算される。
- 問題点
- 長期評価では南海地震と東南海地震の時系列のパラメータを別個のものとして与えているが、単一の時系列とすることの是非。
- 想定東海地震を南海〜東南海地震の系列とは別の独立な地震とすることの是非。
- 想定東海地震の発生確率の根拠をいかに説明するか。なお、今後10年間想定東海地震が発生しない場合、その後の発生確率を0とすることはできる。
- 将来の30年または50年間に想定東海地震の領域(領域Z)が2回震源域となる可能性を認めていることの是非。(想定東海地震が安政東海地震の割れ残りとするなら2回震源域となってもよい?)
D. モデル化案4
- 前提条件
- 歴史的に、南海地震と東南海地震(想定東海地震の領域Zまでが震源域となる場合を含む)は同時(連動)あるいは非常に近接した時期に発生している。
- 想定東海地震は南海地震〜東南海地震の一連の時系列とは別個に単独で発生する可能性がある。
- 時系列のモデル化
- 南海地震と東南海地震(想定東海地震の領域Zまでが震源域となる場合を含む:以下、南海〜東南海地震と記す)は経時的に「単一の更新過程」に従う。
- 想定東海地震は上記の更新過程の系列とは別個に発生するが、南海〜東南海地震と独立ではない。想定東海地震が先に発生した場合には、次の南海〜東南海地震では震源域は想定東海地震の領域Zにまでは及ばないと仮定する。また、南海〜東南海地震が先に発生した場合には、もはや想定東海地震は発生しないと仮定する。なお、想定東海地震が先に発生しても南海〜東南海地震の発生確率は影響を受けないと仮定する。
- 南海〜東南海地震の発生確率算定用のパラメータは、長期評価の東南海地震の値を用いる(表5.2.3-13)。
- 以上の条件で、西暦2004年1月から30年間、50年間の地震の発生確率は次のよう(表5.2.3-14)になる。
(注: 50年程度では2回発生する確率はほぼ0である)
- 一方、想定東海地震の発生確率(=想定東海地震が南海〜東南海地震より先に発生する確率)は、「今後10年間は南海地震、東南海地震より高いが、10年程度で頭打ちとなる」という前提の下に、本資料では30年、50年ともに50%と仮置きしておく(表5.2.3-15)。
- 南海〜東南海地震の震源域については各領域が別個に震源域となるか、あるいは複数の領域が連動して震源域となると仮定する。震源域はそれぞれの領域内で予め設定されたモデルとし、モデルの一部が震源域となる場合は想定しない。
- 南海〜東南海地震が先に発生する場合については、過去の地震のパターンに基づき、明応、慶長、宝永、安政、昭和の5回のうちの2回(慶長、宝永)が3地震の連動(領域X+Y+Z)、2回(明応、安政)が南海地震と東南海地震&想定東海地震の連動(領域X、Y+Z)、1回(昭和)が南海地震と東南海地震が別個(領域X、Y)として各パターンの生起確率を与える。なお、明応の地震は南海地震の発生は確認されていないが、本案では南海地震〜東南海地震を単一の時系列としているために、東南海地震が発生し南海地震が発生しないパターンは考慮できない。したがって、ここでは明応も安政と同じパターンと仮定した。また、南海地震と東南海地震のみの連動(領域X+Y)は過去にはないので、このケースの生起確率は0としている。
- 一方、想定東海地震が南海〜東南海地震よりも先に発生する場合には、その次の東南海地震では震源域は東南海地震の領域(領域Y)のみで、想定東海地震の領域(領域Z)まで震源域が及ぶ可能性は考えない。この場合、過去5回のうちの慶長、宝永の2回が南海地震と東南海地震の連動(領域X+Y)と考え、両地震の連動の確率を2/5(=40%)と仮定する。
- なお、案4では、上記の仮定を設けているため、将来30年あるいは50年の間に領域Zが2回震源域となる可能性はない。
- イベントツリー
- 上記の条件は、南海〜東南海地震と想定東海地震の発生順序によって、その後の地震活動(地震発生の有無、震源域の組合せ)が変わるため、独立な事象の組合せとはならない。そこで、上記の条件を示したイベントツリーを下記(図5.2.3-1)に示す。(確率は2004年から50年間の場合)
- 各ケースの生起確率と地震ハザードの計算方法
- 以上に示したイベントツリーの各ケースの西暦2004年から30年間ならびに50年間の生起確率は表5.2.3-16のようになる。
- 地震ハザードは、上記の各ケースの生起確率に当該ケースの震源域に対応する地震動強さの超過確率を積和することにより算定される。
- 問題点
- 長期評価では南海地震と東南海地震の時系列のパラメータを別個のものとして与えているが、単一の時系列とすることの是非。
- 想定東海地震と南海〜東南海地震との相関性(発生順序に応じて相手方の地震の発生確率や震源域が変わる)を仮定しているが、実例がない状況において、そのシナリオが断定的すぎないか? また、想定東海地震の発生確率(想定東海地震が先に発生する確率)も含めて、一連の事象の生起確率の根拠をいかに説明するか。なお、今後10年間想定東海地震が発生しない場合、その後の発生確率を0とすることはできる。
5.2の参考文献
- 中央防災会議「東海地震に関する専門調査会」(2001):中央防災会議東海地震に関する専門調査会報告,平成13年12月11日.
- 地震調査委員会(2001):南海トラフの地震の長期評価について,平成13年9月27日.
|