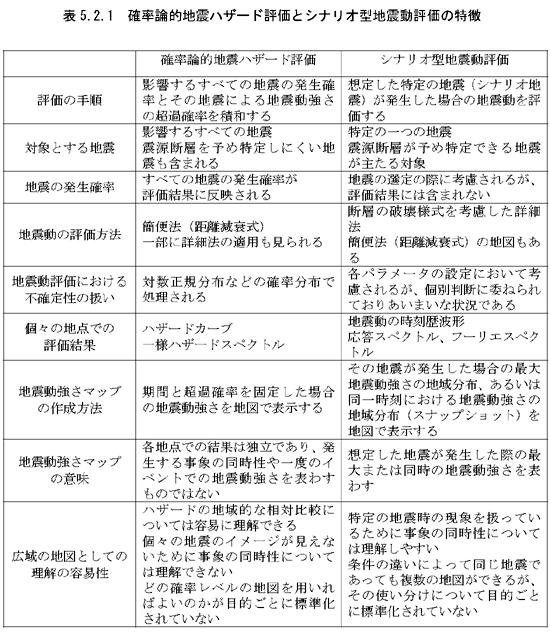
確率論的地震ハザード評価(確率論的地震動予測地図)とシナリオ型地震動評価(震源断層を特定した地震動予測地図)の特徴を比較した表を表5.2.1に示す。
確率論的地震ハザード評価は、地震の発生や地震動の予測に関わる種々の不確定性を確率モデルで表現することにより、全体の不確定性を組織的に定量評価し、不確定性のもとでの意思決定という地震外力設定の問題に対処しようとするものである。その結果は通常ハザードカーブや一様ハザードスペクトルなど、発生確率に対応する地震動強さで表現される。確率論的地震動予測地図は地震ハザード評価結果に基づいて、超過確率のレベルを揃えた場合の地震動強さもしくは地震動強さのレベルを揃えた場合の超過確率の地域的な分布を地図として表現したものである。地震ハザード評価は、予測される地震動の強さとその発生確率との関係(ハザードレベル)を明確にできることが最大の特徴である。
これに対して、シナリオ型地震動評価は過去の地震歴や活断層の分布などの情報を参考にして、将来発生しそうな地震の物理的な諸元をあらかじめ特定の値に設定し、それに基づき地震動の予測を行うものである。構造物の設計用入力地震動を時刻歴波形や応答スペクトルなどにより定める場合、震源断層の諸元やサイトとの位置関係などが明らかなシナリオ地震を設定することにより、断層の破壊様式なども含めて地震動の定量評価を行えるという利点がある。特に兵庫県南部地震で経験したように、被害に結びつく地震動には強い局所性があり、このような地震動の性質を把握するにはシナリオ型地震動評価が有用である。また、広域的な防災対策では、地震によって「一度に」発生する地震動強さの地域分布を知る必要があるため、外力条件としてシナリオ地震を設定することが有効である。確率論的地震動予測地図はサイトごとに独立に解析した結果を地図の形で示したものであって、広域的に「一度に」発生する地震動の分布を表したものではないことに注意が必要である。なお、シナリオ型の地震動予測地図にも「同時(同一時刻)」の地震動分布を示したもの(スナップショット)と、「一度(特定の地震に対する最大)」の地震動分布を示したものがあるが、一般的には後者が利用されている。また、「一度」の地震動分布の中にも単一の評価条件での地震動強さの分布を示したものと、同じ地震で破壊開始点やアスペリティ位置などの一部の条件を変えた複数の評価結果に基づいてその中の最大の地震動強さ(包絡値)を地点ごとに拾い出し、その分布を示したものがある。
個別地点を対象として将来の地震動を予測する場合、地震動の不確定性を考慮できるという点で確率論的地震ハザード評価は有用な手法と考えられる。全国の地震ハザードを同じ尺度で比較するには確率論的な手法に拠らざるを得ない。また、リスクマネジメントへの展開や、地震以外のリスクとの定量比較を行う場合にも確率論的手法が有用である。特に欧米を中心とする諸外国では様々なリスクが確率論的に評価されており、国際化の視点からも確率論的手法を忌避することはもはや許されない趨勢となっている。
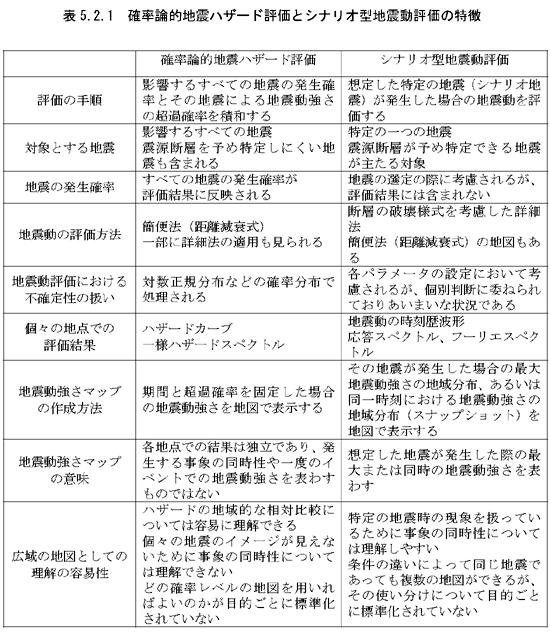
しかしながら、確率論的地震ハザード評価を具体的に利用するにあたっては解決を要する課題も多い。まず、利用目的に応じて意思決定に用いる確率レベルを具体的にいくつにすればよいのかという問題に関して議論が進んでいない。特に兵庫県南部地震のような低頻度の問題に対して確率が利用できるのか、あるいはどのように利用していくのかについて、専門家の間でもコンセンサスが得られていない。関連して、確率論的地震ハザード評価の結果では相対的に発生確率が低い地震による地震動の特徴が反映されにくいという性質があるが、これに対してはシナリオ型地震動評価の補完が必要と思われる。加えて、地震動評価が簡便法にとどまっているという問題も今後解決していく必要がある。
一方、広域を対象とした場合には特定の地震が発生した場合の被害の特徴や被害量の総和を把握したいというニーズが強いが、こうした目的にはシナリオ型地震動評価が有効である。確率論的地震ハザード評価に基づくポートフォリオリスク評価では被害量と対象期間での発生確率の関係を把握することができるが、特定の地震に対する被害をイメージできないという問題点がある。しかしながら、シナリオ型地震動評価では想定地震や震源メカニズム等を選定する手続きに任意性があり、設定したシナリオがどの程度の確率で生起するのかを含めて、設定したシナリオの妥当性をいかに説明するかが課題とされている。こうした点を解決していくために、当面は確率論的想定地震など確率論的地震ハザード評価の再分解の結果とシナリオ地震との関係の明確化や、シナリオ型地震動評価の結果を確率論的地震ハザードの観点からレビューすることで互いの関係を定量評価していくことが重要である。こうした事例を積み上げることによって、確率論的地震ハザード評価を活用していく場合に要請される確率レベルの具体化に対する理解も深まっていくことが期待される。
|
|
|
| ← Back | Next → |