| (4.5.1) |
ここでは、ライフラインの特徴である「使用性」に注目して補強の箇所や優先度を検討する地震リスクマネジメントについて最近の考え方1)を述べる。その中で、地震動予測(シナリオ型地震動、確率論的な地震動)がどのように適用できるのかを考察する。事例として電力流通設備を構成する変電設備を対象とする。変電設備は、主回路と呼ばれる重要機器では動的地震力(地表面で0.3G)による設計が1970年代の終わりころから適用されてきている。兵庫県南部地震を含め、この設計法によった機器の被害が重大な供給支障につながった例はないが、今後予想される地震動のレベルが設計基準で考慮している動的地震力を超過する可能性がある場合には、適切な補強対策などが求められる。
以下にはレベルの異なる5段階のリスクマネジメント手法を提案する。レベルが進むにつれて、より詳細手法となるが、解析に必要なデータも増える。
(1) レベル0
レベル0は、現行の設計地震力を設備に作用させた場合、最も応力が集中する部位に生起する発生応力(STRSSoccur)と許容応力(STRSSaccept)との関係で、補強・更新の判断を行う方法である。現実の電力流通設備は膨大な数であり、その中には現行の設計基準の適用以前に設置された設備も多くあることから、現行基準を満たしているか否かのスクリーニングをするには有効な手法といえる。補強・更新の判定は、式(4.5.1)の判定式により行う。
| (4.5.1) |
ここで、![]() は、補強・更新の判断をする指標となる。
は、補強・更新の判断をする指標となる。
この方法の範囲では地震動を予測することは不要である。しかしながら、近年、設計地震力として想定されている加速度レベルを越える加速度が数多く記録されていることを考えると、特に断層近傍の地域に位置する設備の耐震性は保証できない。また、問題がある設備を特定できたとしても、耐震補強・更新の対象となる設備数が多い場合、対策の優先順位の決定を客観的に行うことが難しい。
(2) レベル1
レベル1は、対象となる地域にシナリオ地震を設定し、確定的に被害想定を行う方法である。一般に自治体やライフライン事業体における被害想定に用いられる方法である。シナリオ地震をもとに、各設備に作用する地震動強度(地表面最大加速度など)を想定し、設備に発生する応力等を推定する。損傷の有無の判断は式(4.5.1)と同様である。この方法によれば、補強・更新の対象となる設備をある程度絞り込むことが可能となる。ただし、対象となる地域に支配的となるシナリオ地震を特定できない場合はこの方法は適用しにくいので、レベル0の方法に準拠するなどする。
(3) レベル2
レベル2は、レベル1の方法論を確率的に扱ったものである。対象となる設備に作用する地震動強度を推定するために、シナリオ地震または確率論的な地震動を導入した評価を行う。一方、想定される地震動強度に対する各設備の被害の可能性は、各設備の部材(がいしなど)の材料強度のばらつきを考慮したり、既往の地震被害の統計データを活用したりして確率的に評価する(一般に、フラジリティ評価と呼ばれる)。ハザードおよびフラジリティの評価から個々の設備の被害確率を計算し、その値がある閾値を超えているかどうかで、損傷の判定を行う。式(4.5.2)に被害確率の定義を示す。
| (4.5.2) |
ここで、![]() は、対象となる設備
は、対象となる設備 ![]() 直下に作用する地震動強度
直下に作用する地震動強度 ![]() が、設備耐力
が、設備耐力 ![]() (本論では、地表面の地震動強度の関数として与える)を超える確率を示す。
(本論では、地表面の地震動強度の関数として与える)を超える確率を示す。![]() は、設備
は、設備 ![]() 直下に作用する地震動強度の関数として与えられる設備耐力
直下に作用する地震動強度の関数として与えられる設備耐力 ![]() の確率密度関数を示す。
の確率密度関数を示す。 ![]() は、設備
は、設備 ![]() 直下に作用する地震動強度Sの確率密度関数を示す。
直下に作用する地震動強度Sの確率密度関数を示す。![]() は、地震動強度
は、地震動強度 ![]() の確率分布関数を示す。なお、1−
の確率分布関数を示す。なお、1−![]() は地震動強度の超過確率に相当する。
は地震動強度の超過確率に相当する。
上記で示したレベル0〜2は、部材に発生する最大応力が許容応力を超えているかどうかを判断基準にする考え方である。すなわち、想定地震力に対して設備に被害が生じないように補強・更新対策を行うことを前提とする。ただし、レベル2の方法論では、個々の設備に対する被害の生じやすさが確率値として評価されるが、補強・更新を行う判断基準(許容する被害確率)は予め明確にしておく必要がある。
(4) レベル3
レベル3は、耐震対策以外の効果も総合的に評価して、補強・更新すべき設備の優先順位を決定することを主な目的としている。すなわち、設備の耐震性、システムの持つ冗長性および事後の復旧対応能力を考慮した地震後のシステム性能評価を基に、個々の設備の補強・更新がシステム性能に与える影響の感度を見ながら優先順位を設定することを意図している。
この場合、地震動強度の確率分布Fsi(r)は、確率論的な地震動のような地震の発生頻度を考慮しないで、シナリオ地震による強度分布として定義される場合が扱いやすい。その理由は、確率論的な地震動では、複数の地震の影響が同時に広域のライフライン施設への地震動として現れるので、ライフラインのシステムとしての機能損傷が正確に求められないことによる。これを克服するためには、影響の大きい(ライフラインシステムのどこかにレベル2地震動を与えると思われる)複数の地震シナリオを確率論的地震ハザードの再分解の方法などにより設定し、それらに対して個別にネットワークの機能損傷評価を行い、システムに影響の大きな地震シナリオを抽出する。
システムの性能は、リスクカーブによって評価する。図4.5.1は、リスクカーブの概念図を示す。本論では、対象とする電力システムの供給支障電力とその超過確率との関係を定義した曲線を、リスクカーブと呼ぶ。たとえば、想定地震力に対して発生した供給支障電力が、補強・更新により低減されると、リスクカーブは左下方にシフトする。このため、リスクカーブの相対的な比較から、補強・更新すべき設備の優先順位を決定することが可能となる。
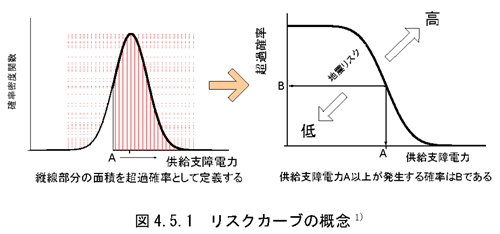
(5) レベル4
レベル4はライフサイクルマネジメントであり、レベル3の考え方をさらに進め、コスト評価に基づく費用対効果分析にポイントをおいた考え方である。想定地震力に対する地震対策コストと損失との間にはトレードオフの関係がある。地震対策コストを多くとれば、リスクレベルは低くなり、損失も小さく抑えることができる。逆に、地震対策コストを少なくすれば、リスクレベルは高いままとなり、損失が大きくなってしまう。このような地震対策コストと損失の関係を定量的に分析することで、適切な設備投資を実現する補強・更新戦略が策定できる。
図4.5.2は、コスト評価で一般に必要となる費用項目を示す。地震対策コストは、事前対策費用・事後対策費用およびリスク転嫁費用からなる。被害コストは、供給者サイドと需要家サイドに二分される。供給者サイドに生じる被害コストは、復旧コスト・地震被害により生じる電力販売収入減(損失)および供給支障により需要家に支払わなければならない補償コストからなる。需要家サイドに生じる被害コストは、停電コストである。こうしたコスト評価を行い、費用負担が発生する対象者(電気事業者や電力市場)が誰になるのかを明確にして、それらに関わる総費用がもっとも少なくなるように補強・更新を検討することが、レベル4の基本的考え方となる。
なお、実務の現状では、電力流通設備の更新戦略を策定する場合、低頻度で発生する地震リスクは、更新優先順位決定に反映されていない。これを改善するために、レベル4の考え方では、地震リスクはもとより、経年劣化や塩害など通常の更新計画で考慮されるリスクに対処するため、トレードオフの関係にある費用構造を他の災害事象(マルチハザードと呼ぶ)に対しても検討する。すなわち、レベル4では、設備のライフサイクルにわたって問題となるマルチハザードを対象として、費用対効果分析が可能となることを目標としている。現状では、マルチハザードについての研究は途上であり、ハザードによる影響が互いに独立であると仮定しての扱いは可能な段階にあるが、複数ハザードによる影響に関係が認められるようなケース(たとえば、地震+津波、地震+火災)の扱いについては今後の課題である。
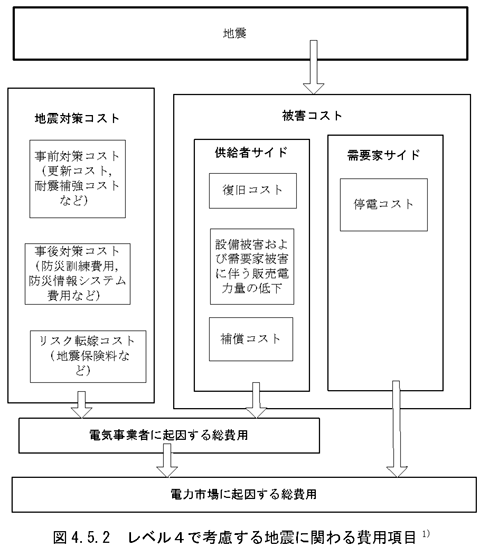
マルチハザードに対してリスクマネジメントを計画する場合、それぞれのハザードに対してのリスク指標が共通であることが望ましい。たとえば、停電の場合であれば、年間の停電発生時間が分かりやすい指標になる(通常、供給信頼度と呼ばれる)。そのためには、ハザードに関しても、年発生確率の情報が必要である。塩害によるがいし汚損であれば、過去の統計からの台風の襲来確率がベースとなる。劣化であれば、常時の事故統計やメンテナンス記録から、対象機器の年間故障率がベースとなる。地震の場合についても、ここで発生頻度の導入が必要になる。研究途上の課題ではあるが、対象のライフラインシステムに脅威となるシナリオ地震の発生頻度分布や最新活動時期などの研究成果を反映していくことが期待される。
|
|
|
| ← Back | Next → |