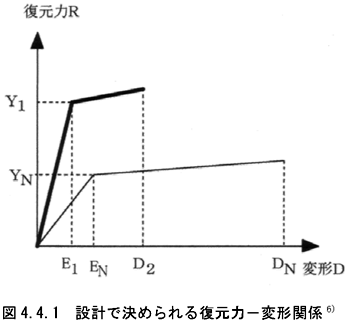
レベル2地震動対応の設計法が高度に整備されてきている一方で、レベル1地震動対応の設計法が依然として十分な議論のないまま震度法由来の弾性設計の範囲に留まっていることには問題がある。何が問題かというと、従来の震度法由来の弾性設計は、もともと安全性照査であったはずなのだが、2段階設計に移行した時点で使用性照査にすりかわったことである。このことの弊害はまだあまり表面化してはいないが、後述するように技術の健全な進歩を阻害する可能性がある。
土木学会地震工学委員会(耐震基準小委員会)では、この点に鑑みて、新しい設計体系への移行を検討しており、平成15年11月には「土木構造物の耐震性能設計における新しいレベル1の考え方(案)」(ワーキンググループ主査:澤田純男 京大助教授)をとりまとめた。以下に、その報告書6)に基づいて要点を紹介する。この新しい設計体系の中では、シナリオ型地震動評価と確率論的地震ハザード評価の両方が有効に利用できる。
(1) レベル1地震動に対する性能目標とは
現在では、終局限界状態を照査するレベル2 設計法が整備され、ほとんどの構造物の断面がレベル2 で決められるようになってきているが、レベル1 設計が不要であるという意見は土木技術者からあまり聞かれない。たとえレベル2 設計で構造物系全体が崩壊しないように設計されていたとしても、レベル1 設計で弾性限界を規定することによって中小の地震での被害をコントロールすることが必要であると考えられているからであろう。
しかしながら、現在のレベル1 設計法が、この命題に対して合理的であるという根拠はない。レベル1 設計に用いる入力地震動として、「供用期間に1 〜2 回発生する確率を持つ地震動」という定義に従って例えば50 年期待値に対応する地震動を用いたとすると、50 年間に弾性限界を超えない確率がポアソン過程なら約37%になるように構造物を設計することになる。しかしながら、この確率が37%でなければならない根拠は明らかでない。また、弾性限界を超える確率が残り63%となるが、それがどの程度の被害となるのか、ほとんど補修を必要としない程度となる確率がどれぐらいか、建設コストに比べて十分に大きな復旧コストとなる確率がどれぐらいか、等は一切考慮されない。
実際にメインテナンス計画を考える上で重要なのは、無被害の確率よりも、被害が出たときにどれぐらいの被害となって、その復旧にどれぐらいのコストと日数が掛かるか、である。
レベル1 設計で実現すべきは、頻繁に弾性限界を超えることによって、点検コストや復旧コスト、さらには点検や復旧のために供用を一時停止することによる「経済的被害」が過大にならないように構造物を設計することである。すなわち、修復に伴う経済性の照査を求められているものと考えることが妥当である。
そこで、レベル1 に対する性能目標として、「地震時および地震後に、構造物の機能が、経済的に維持できる」とすることが提案されている。
(2) 現在のレベル1 設計法が技術的進歩の障害となっている点
ここでは簡単のため、構造物の設計を、弾性限界と許容塑性率を決めることと単純化して解説する。
弾性限界をコントロールするのは主に断面形状や断面積であり、場合によっては材料の選択によって調整することもある。許容塑性率を制御するのは、主に鋼構造、鉄筋コンクリート構造、複合構造などの構造形式であり、場合によっては帯鉄筋量などの構造細目によって調整することも考えられる。現在の二段階設計法では、図4.4.1の太線で示されているように、レベル1 で弾性限界(Y1 )を規定し、その断面でレベル2 地震動に対する最大応答D2 を求め、これによる塑性率(D2 /E1 )が許容塑性率を超えないかを照査している。
ここで、図4.4.1 の細線のように、弾性限界をYN に引き下げることを考える。弾性限界を引き下げれば小さな断面で済むので、剛性は小さくなり、弾性限界に対応する変形EN もE1 より大きくなる。この断面のレベル2 地震動に対する最大応答はエネルギー一定則にほぼ従うと考えればD2 よりかなり大きくなりDN となる。しかし、許容塑性率が十分大きくとれる構造形式を採用すれば、このときの塑性率(DN/EN)を許容塑性率より小さくすることが可能である。さらに変位一定則として良く知られているように、建設地点の地震動特性によっては、DN とD2 はほぼ同じである場合も考えられる。この場合は特に構造形式を変更しなくても、断面を小さくすることによって何ら安全性を損なうことは無いどころか、反対に塑性率に余裕が生じることになる。
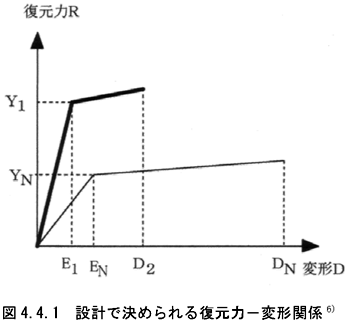
このように弾性限界を引き下げた設計をすることによって、建設コストを圧縮することができるが、これによって発生する問題は何か? それは比較的小さな地震動に対しても弾性限界を簡単に超えて、損傷が発生する可能性があることである。それでは弾性限界を超えて損傷が発生すると、何が困るか? それは損傷を補修する必要が生じるので補修するためのコストが発生することと、補修のために供用を一時停止すると周辺社会に与える間接被害がコストとして発生することである。このような概念を表したのが図4.4.2である。
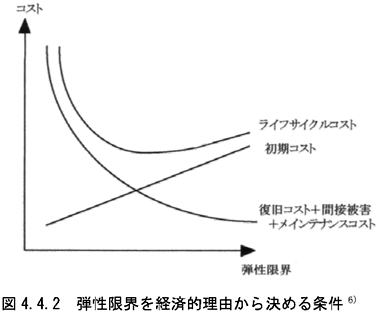
図4.4.2の縦軸はコスト(金額)、横軸は弾性限界の大きさである。したがって、建設コスト(初期コスト)に加えて供用期間中に耐力を維持するためのメインテナンスコスト、供用期間中に発生するであろう地震被害に対する復旧コストと復旧期間中の供用停止による収入減(直接被害)と、供用停止が社会に与える経済的波及効果(間接被害)の総額(ライフサイクルコスト)が大きくならないなら、断面を小さくして弾性範囲を引き下げることが可能であると考えられる。理想的にはライフサイクルコストが最小になるような断面設計をすればよい。
(3) 経済性照査の基本手順
現状のレベル2 設計をそのままにして、弾性限界をどこまで下げられるのかを、あるいは弾性限界をどこまで上げなければならないかを、経済的視点から決めるべきというのが主張である。すなわち、性能目標としての「地震時および地震後に、構造物の機能が、経済的に維持できる」を満足しているかどうかを、初期建設コストと、ライフサイクル全期間に対する地震時および地震後の復旧コストと間接被害の期待値の和、すなわちライフサイクルコストを最小化させるような設計となっているかで照査することが提案されている。
| (4.4.1) |
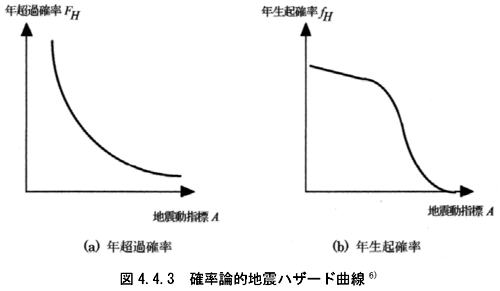
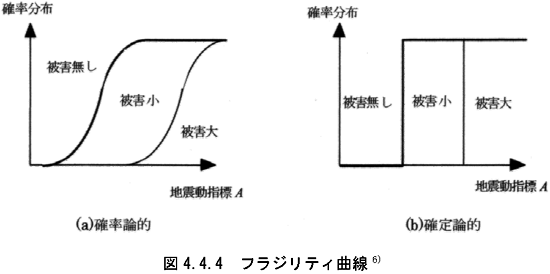
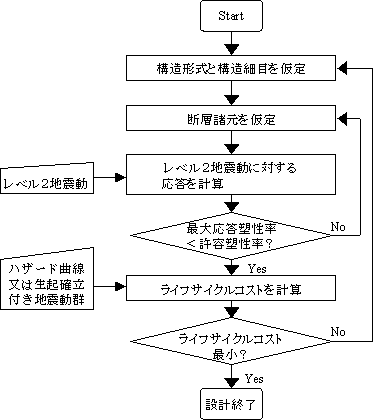 |
|
|
|
| ← Back | Next → |