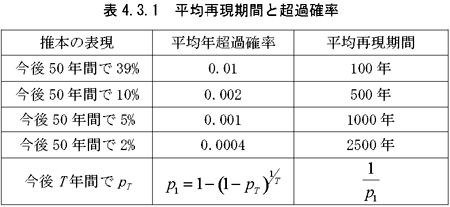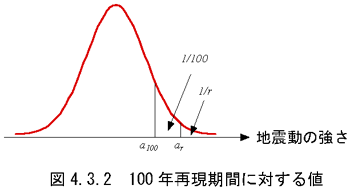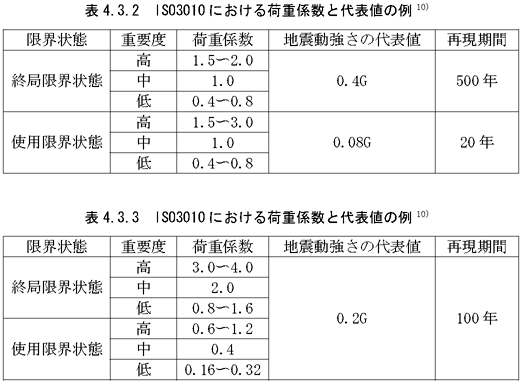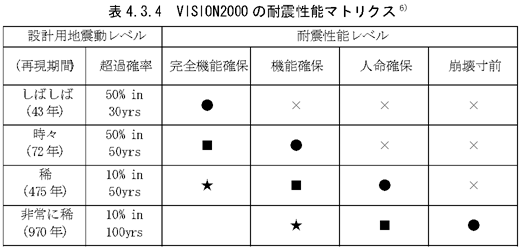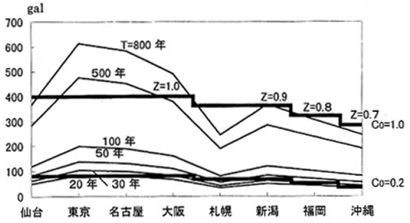4.3.3 確率論的地震動予測地図の利用
(1) 耐震設計法への活用
図4.3.1に示した荷重効果  の確率分布は建設地点に置ける地震動強さの確率分布に他ならない。確率論的地震動予測地図では、指定超過確率(例えば、今後50年間で○%)の下での地震動の大きさが計測震度を用いて表現されている。これを設計に用いる場合には、前節で示したように、地震動強さの確率分布形の情報が必要となる。これには、複数の指定超過確率と地震動の大きさの対応関係から、地震動の確率分布を近似的に評価できる。米国では、極値II型分布を仮定してその分布形を定めるパラメータを求め、耐震性評価に有効に用いている事例もある7)。
の確率分布は建設地点に置ける地震動強さの確率分布に他ならない。確率論的地震動予測地図では、指定超過確率(例えば、今後50年間で○%)の下での地震動の大きさが計測震度を用いて表現されている。これを設計に用いる場合には、前節で示したように、地震動強さの確率分布形の情報が必要となる。これには、複数の指定超過確率と地震動の大きさの対応関係から、地震動の確率分布を近似的に評価できる。米国では、極値II型分布を仮定してその分布形を定めるパラメータを求め、耐震性評価に有効に用いている事例もある7)。
一旦、確率論的地震動予測地図を用いて、建設地点に置ける地震動強さの確率分布が得られたなら、図4.3.1に示した、(d)確率に基づく設計が可能である。ただし、地震動として評価対象期間を設定し、当該期間の最大値の確率分布を用いることになる。日本建築学会の限界状態設計指針3)では、終局限界状態に対して50年最大値分布を、使用限界状態に対しては年最大値分布を用いている。当然ながら建物の供用期間が長い場合には、その供用期間に応じた地震動最大値の分布を用いることが望ましい。
(b)の方法では、設計用地震動の大きさを再現期間と対応させて設定する方法である。「再現期間△年の地震動強さ」の評価には、地震動がある閾値を超過する事象の発生をベルヌーイ試行列と仮定する方法が一般的である。具体的には、今後
 年間で確率
年間で確率  となる地震動強さは、下式を用いて
となる地震動強さは、下式を用いて  年間でならした平均再現期間
年間でならした平均再現期間  と関連させることができる8)。
と関連させることができる8)。
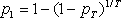 |
(4.3.1) |
ここに、 は1年当たりの超過事象の確率であり、上式を用いれば表4.3.1のような平均再現期間との対応関係が得られる。
は1年当たりの超過事象の確率であり、上式を用いれば表4.3.1のような平均再現期間との対応関係が得られる。
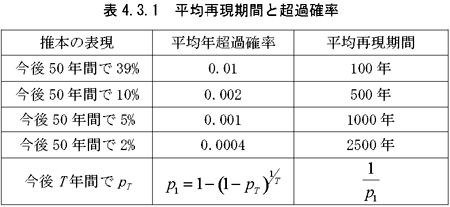
日本建築学会の荷重指針9)においては、再現期間100年に対応する値を、図4.3.2に示すように「荷重の基本値」として定義し、時間変動する荷重(地震、風、雪)の大きさの目安を与えている。ただし、限界状態設計に用いる場合には、地震動強さのばらつきも含めた確率分布形の情報が必要であることは言うまでもない。
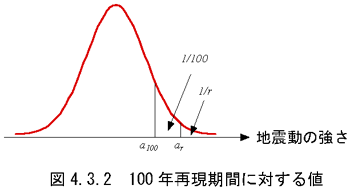
以下には、確率論的地震動予測地図の利用を考える上で、確率に基づく設計の具体事例をいくつか紹介する。
ISOの地震荷重規格10)
建築・土木構造物の地震荷重については、今年、国際標準化機構(ISO)で一般構造物を対象にした地震荷重規格(ISO3010)が改訂されたばかりであり地震荷重に関する世界共通の考え方が提示された。その骨子は、ISO2394「構造物の信頼性に関する一般原則5)」の設計の基本に基づき、まず、1)ふたつの設計上重要となる終局、使用限界状態の定義を明確にしたこと、2)夫々の限界状態に対して設計荷重の構成が示されていること、が特徴であろう。
本規格では、まず、耐震設計の基本的考え方が示されており、「耐震設計は、地震時における人身への危険防止、重要なサービスの維持、経済的な損失の最小化の目的で実施される」としている。そして、ふたつの限界状態に関しては、全ての地震から構造物を完全に守ることは経済的に不可能なために、起こるかも知れない大地震動に対しては構造物の崩壊を防止し人命を守り〔終局限界状態〕、使用期間中に起こる中地震動に対しては構造物の被害を許容限界以内におさめる〔使用限界状態〕ことを目標にしている。この限界状態の考え方は、昨今の性能設計の根幹を成す重要な概念である。また、この規格の附則には、地震荷重の大きさを設定する考え方が示されており、確率・統計的な考え方がベースとなっている。表4.3.2及び4.3.3は、各々の限界状態に対して再現期間を定めて地震荷重の大きさを定めている。また、対象建物の重要度に応じて荷重係数を変化させている。
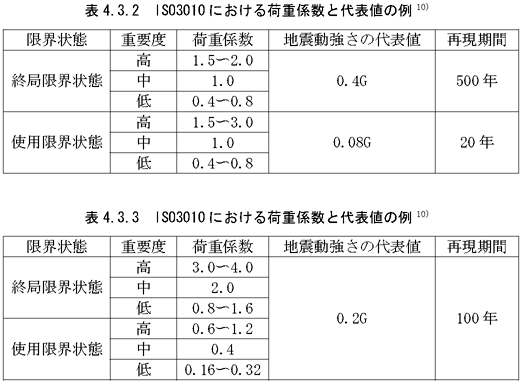
VISION20006)
カリフォルニア構造技術者協会(SEAOC: Structural Engineers Association
of California)より「Vision 2000 - 性能に基づいた建築物の耐震工学6)」と題するレポートが発行され、性能明示型の新しい耐震設計体系の骨格と設計手法を提示している。これは、設計用地震荷重レベルをその地域の再現期間あるいは発生確率で複数定義し、それらの地震動レベルにおいて地震時の性能レベルを別途定めた性能マトリクスを目標に設計するものであり、それらの性能レベルは建物の被害状態と直接対応するようになっている。表4.3.4がVision2000で提案された耐震性能マトリクスである。この考え方は、米国統一耐震規定IBCにおいても採用されている。
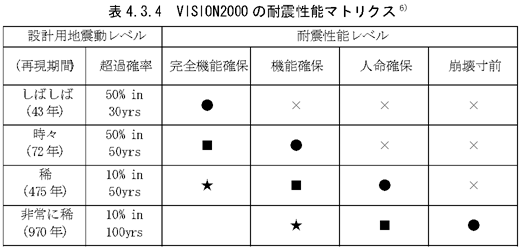
日本建築学会の限界状態設計指針3)
日本建築学会では、建築物のより合理的な構造設計法確立を目指した活動を実施しており、その中で、建築物の限界状態設計指針3)が2003年に刊行された。これは建築物の構造形式〔鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造、など〕によらない統一的な共通の設計の枠組みを提供することを目的に、確率・統計的手法に基づいて目標安全水準を定めて設計荷重や設計耐力を決めてゆく合理的な方法である。ここでは、荷重・耐力係数設計法が採用され、荷重の発生頻度や荷重強さのばらつきを直接的に反映した設計式を用いている。
建築構造物に要求される条件として、安全性と使用性に関わるものがあるが、それらを設計で考慮する限界状態として定め、それらに対して、荷重・耐力係数を定めて、各部設計の荷重組合せ方法を示している。荷重係数は、荷重の種類や特性〔発生頻度は荷重作用時間〕に応じて荷重組合せ係数が定められる。なお、この設計式の一番の利点は、設計荷重や耐力が目標安全性水準と直接関連していることであり、現行設計法にはない重要な特徴である。
建築基準法における地震荷重の確率的評価11)
1998年6月に建築基準法が大幅改定・公布され、 2000年6月には基準法施行令が公布された。この改定の目的は、従来の仕様に基づく規定から性能に基づく規定への大幅改定であった。
要求耐震性能としては、最大級の地震に対して人命保護(各階の崩壊を生じさせない)、建物供用期間中に一度以上遭遇する地震に対しては、損傷防止(構造安全性の維持に支障のある損傷を生じさせない)となっており、前者に対しては、建物の変形量を評価するものとしており、等価線形化手法と応答スペクトル法を組み合わせた「限界耐力計算」と呼ばれる新たに開発された検証法を用いることが謳われている。残念ながら、地震荷重の大きさや表現については旧基準法のものと基本的に変わっておらず、確率・統計的な考え方を盛り込むことが今後の大きな課題となろう。
この改定に先駆けて、建設省主導で総合技術開発プロジェクト「新建築構造体系の開発」が実施され、今後の建築設計において、建築物の安全水準をどう考え、どのように扱うべきかについて膨大な検討がなされた。図4.3.3は、全国8都市における旧建築基準法で定められる地震荷重を、建築学会の荷重指針の統計資料を用いて再現期間で表したもので、地域によって大きな差があることがわかる。同図より、建物の性能水準を全国で均一にするには、現行規準に用いられている地震地域係数Zにもっと差をつける必要があることがわかる。これらは、確率論的地震動予測地図を用いて検討することができ、既往規準の不具合を確率的な視点から再評価することが可能である。
図4.3.3 荷重指針9)のデータの基づく、全国各都市における地震荷重の再現期間
(Z:旧基準の地震地域係数)11)
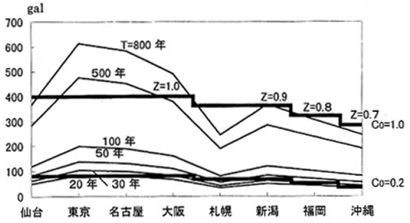 |
(2) 簡易建築物の耐震評価への活用
現在の確率論的地震動予測地図は地表面の計測震度に対して作成されている。これは国民が慣れ親しんでいる震度を用いることにより、国民の間で地震防災意識を喚起させる利点がある。地面の揺れを震度というわかりやすい表現を用いれば、個人住宅の耐震設計・診断に有効に活用できる。
個人住宅の耐震診断等においては、その評価は簡便な方が望ましい。そこで以下には、震度で表された確率論的地震動予測地図を用いて建物の簡易耐震診断が簡単にできる方法を紹介する。
個人住宅の耐震性能の内、建物の安全性を例にとって説明する。いま、建物が今後50年以内に地震により建物の安全性が損なわれ崩壊する確率
 は次式で評価することができる。
は次式で評価することができる。
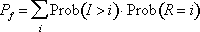 |
(4.3.2) |
ここに、 は今後50年間に建物建設地点の計測震度
は今後50年間に建物建設地点の計測震度  が
が  を超える確率、
を超える確率、  は対象建物の安全性を損なわせる地面の揺れが
は対象建物の安全性を損なわせる地面の揺れが  となる確率であり、建物の強さを震度で表現したものである。計測震度
となる確率であり、建物の強さを震度で表現したものである。計測震度  に関する総和は、(
に関する総和は、(  =3,4,5弱,5強,6弱、6強、7)とする。
=3,4,5弱,5強,6弱、6強、7)とする。
確率論的地震動予測地図では対象地点において今後50年間に計測震度Iがiを超える確率
 が評価されており、計測震度に関するハザード曲線から容易に評価することができる。また、上式では対象建物の強さが地表面震度で表されている必要があるが、これは、建物の脆弱性曲線を計測震度で表したものに他ならず、既往の建物の脆弱性曲線に関する研究成果を活用することもできる。建物の耐震補強や新築建物の耐震設計においては、2003年に施行された住宅の品確法や性能表示制度と関連づけられることが可能で、国民の住宅性能への関心度を高めることに役立つであろう。
が評価されており、計測震度に関するハザード曲線から容易に評価することができる。また、上式では対象建物の強さが地表面震度で表されている必要があるが、これは、建物の脆弱性曲線を計測震度で表したものに他ならず、既往の建物の脆弱性曲線に関する研究成果を活用することもできる。建物の耐震補強や新築建物の耐震設計においては、2003年に施行された住宅の品確法や性能表示制度と関連づけられることが可能で、国民の住宅性能への関心度を高めることに役立つであろう。