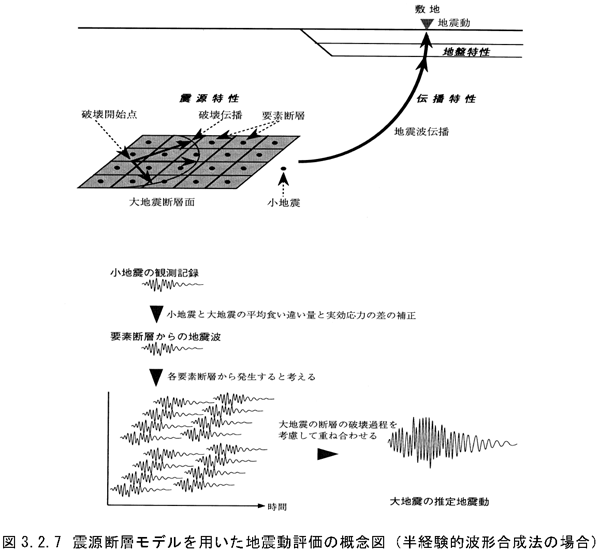
(1)震源断層モデルを用いた地震動の評価手法
主な震源断層モデルの概要について示す。
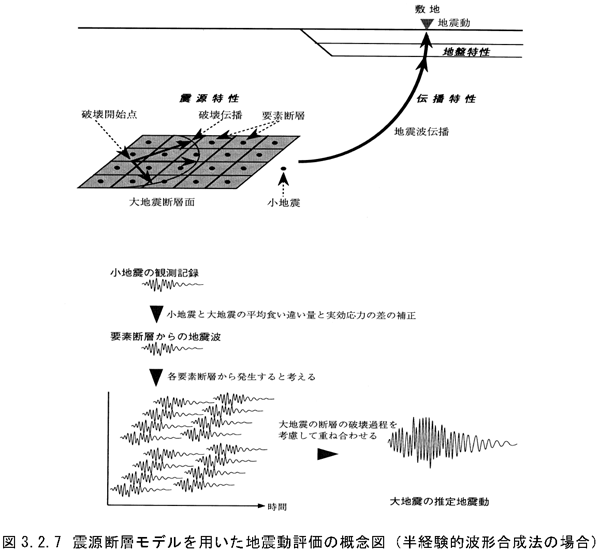
(2)震源断層モデルを用いた地震ハザード評価手法
震源断層モデルを用いた地震ハザード評価手法としては、独立行政法人原子力安全基盤機構の手法5)が公開されている。同手法は、半経験的波形合成法を用いたものであり、その評価手順は図3.2.8に示す次の6ステップからなる。
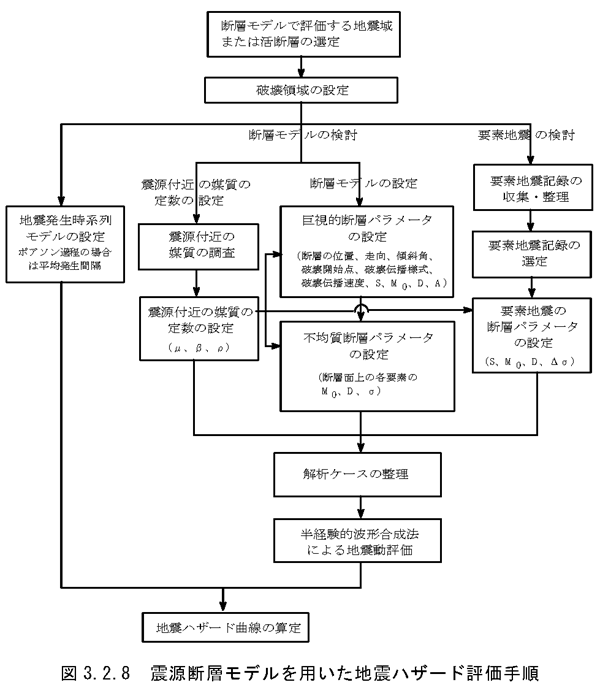
①破壊領域の設定
地震ハザード評価に大きな影響を及ぼす震源断層は、サイトから近距離にあり、かなりの規模を有する断層が想定される。従って、活断層やプレート境界で発生する大規模な地震のように震源域が特定し易く、その規模も比較的特定しやすい断層が対象となる。
②地震の発生確率の算定
地震の発生時系列モデルは、定常あるいは非定常ポアソン過程でモデル化される。
③震源断層モデルの検討
| ・断層面積( |
: | 推定 |
| ・断層の位置 | : | 走向、傾斜角、すべり角 |
| ・破壊開始点 | : | 緯度、経度、深さ |
| ・破壊伝播様式 | : | 例えば、同心円状 |
| ・静的応力降下量( |
: | 例えば、海溝型地震の平均的な値(30bar) |
| ・地震モーメント( |
: | |
| ・平均すべり量( |
: | |
| ・破壊伝播速度( |
: | 例えば、 |
| ・立ち上がり時間( |
: | 例えば、 |
| ・アスペリティの個数・位置:推定 | |
| ・アスペリティの総面積( |
|
| ・個々のアスペリティ(半径 |
|
| ・個々のアスペリティの地震モーメント( |
|
| : |
|
| ・個々のアスペリティの応力降下量( |
|
| : |
|
| ・背景領域断層パラメータ(面積、平均すべり量、地震モーメント、応力降下量) | |
④ 要素地震の設定
要素地震の設定は、対象サイト周辺における観測波形から選択する。サイト周辺での中小地震の観測波形を用いる場合には、次の要素地震の断層パラメータを設定する。
⑤ 地震動評価
③の震源断層モデルと④の要素地震を用いて地震動を評価する。ハザード評価における地震動は、断層パラメータの不確実さを考慮して評価される。具体的な例としては、破壊開始点、各セグメントのアスペリティ個数及び位置、アスペリティの応力降下量、要素地震波の種類、高周波遮断特性等を対象としてこれらの組み合わせをロジックツリーとして表す。
⑥ 地震ハザード評価
②の地震発生確率と⑤の地震動の最大加速度からハザード曲線を評価する。評価した地震動の最大加速度あるいは応答スペクトルと年発生回数の対応表を作成し、その年発生回数を累積して年累積回数を求め、定常ポアソン近似してハザード曲線を評価する。
(3)評価例
上記⑤で述べたように、断層パラメータの不確実さを考慮して、破壊開始点、各セグメントのアスペリティ個数及び位置、アスペリティの応力降下量を対象としたロジックツリーと、これに基づき作成した地震ハザード評価結果の例を図3.2.9に示す。
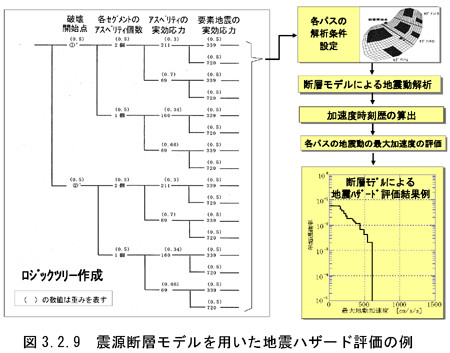
|
|
|
| ← Back | Next → |