|
3.4.4 その他の地震のうちグループ3,4,5の地震
A. グループ3,4,5の地震の定義
長期評価部会では、「その他の地震」のうち震源が予め特定しにくい地震をグループ3,4,5の3つに分類しており、それぞれを以下のように定義している。
| グループ3 |
: |
海溝型地震として扱えるプレート境界で発生する大地震以外の地震 |
| グループ4 |
: |
沈み込むプレート内地震 |
| グループ5 |
: |
陸域の地殻内で発生する地震のうち震源を予め特定しにくい地震 |
グループ3と4の地震は、それぞれ太平洋プレートに関連するものとフィリピン海プレートに関連するものに分けることができるが、今回のサンプル版の作成には、試作領域に対する影響が小さいと考えられる太平洋プレートに関連する地震は考慮しない。
B. モデル化の基本的な考え方
グループ3,4,5の地震は、過去に発生した地震のデータに基づき、地震の発生場所、規模、頻度をモデル化する。この際、地震地体構造や震央分布等に基づいて区分された地震活動域を単位として評価する方法(以下、地域区分する方法)と、機械的に区分した東西南北0.1
度のメッシュを単位として評価する方法(以下、地域区分しない方法)の両者を用いる。前者は損害保険料率算定会(2000)で用いられている手法に準じたもの、後者はFrankel(1995)におけるsmoothed
seismicity の考え方に準じたものである。両者の大きな違いは、地震活動度が均一と考える領域の大きさである。地域区分する方法での地震活動域は一般に0.1
度のメッシュよりも大きく設定されるため、地震発生頻度の地域分布のコントラスト(最大と最小の頻度の比および頻度の高低の距離による変化の程度)は、地域区分しない方法による方が強くなる。
地震の規模別発生頻度は、指数分布(Gutenberg-Richter の関係)に従うものとする。
地域区分する方法では地震活動域ごとのデータを、地域区分しない方法ではメッシュごとのデータをそれぞれ用いることにより、規模別発生頻度を評価する。この際、Gutenberg-Richter
式のb 値は地震活動域あるいはメッシュごとに算定はせず、全領域で一定値とする。最大マグニチュードは地震活動域ごとに設定し、地域区分しない場合には当該メッシュの中心が属する活動域の値を用いる。ハザード評価に用いる最小マグニチュードは、地震活動度の評価に用いる最小マグニチュードによらず一律5.0
とする。
地震の深さは、地震活動域ごとに一定値とし、地域区分しない場合には当該メッシュの中心が属する活動域の値を用いる。
地震の発生時系列は、定常ポアソン過程とする。
C. モデル化の手順と条件(グループ3,4,5に共通する事項)
(1)使用する地震データ
以下の2 種類のデータを用いる。
- 宇津カタログ(宇津, 1982; 宇津, 1985)のうち1885 年から1925年のマグニチュード6.0以上のものと、1926 年以降の気象庁のデータのうちマグニチュード5.0以上のものを組み合わせたもの(以下では「中地震」と呼ぶ)
- 1983 年以降の気象庁データのうちマグニチュード3.0以上のもの(以下では「微小地震」と呼ぶ)
1994年以降の地震のマグニチュードの値は、気象庁地震火山部(2001)の別表に示された17
地震についてのみ修正をしている。
サンプル版の作成では、マグニチュード6.0 以上の地震の発生後90 日以内に、震央を中心とする次式(建設省土木研究所, 1983)で表される面積A (km2) の円内で発生した地震を余震とみなし、機械的に除去する。 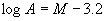 (3.4.4-1) (3.4.4-1)
前震および群発地震は除去していない。前震、余震、および群発地震の除去方法については、次年度以降検討していく必要がある。
なお、地震データからは、別途モデル化される地震(98 活断層帯、海溝型地震、グループ1の活断層)と対応するものは除去する。
(2)地震データのグループ分け
(1)に示した地震のデータは、料率算定会を参考に以下の手順に従ってグループ分けする。図3.4.4-1〜図3.4.4-3 に、料率算定会による地震活動域を示す。
- 1) グループ5の地震に該当する地震の抽出
- 震央が料率算定会の上部地殻内の地震活動域に入り、震源深さが25km 以浅(海域の地震活動域では40km以浅)の地震をグループ5の地震に該当する地震とする。
- 2) フィリピン海プレートに関連するグループ3,4の地震の抽出
- 1)で選定された地震を除去した地震データの中から、震央が料率算定会のフィリピン海プレートの地震活動域に入るものをフィリピン海プレートに関連するグループ3,4の地震とする。ただし、太平洋プレートの地震活動域と重複する部分については、60km以浅のものをフィリピン海プレートの地震とみなす。上部地殻内の地震活動域と重複する部分は、25kmより深い地震のみが用いられている。
- 3) 太平洋プレートに関連するグループ3,4の地震の抽出(サンプル版では対象外)
- 1)と2)で選定された地震を除去した残りの地震データの中から、震央が料率算定会の太平洋プレートの地震活動域に入るものを太平洋プレートに関連するグループ3,4の地震とする。上部地殻内の地震活動域と重複する部分は、25kmより深い地震が、フィリピン海プレートの地震活動域と重複する部分については、60km
より深い地震のみが用いられる。
- 4) フィリピン海プレートのグループ3と4の地震の分離
- 地震のデータの段階では両者は分離せず、地震の発生頻度の算定後に分離する。分離の具体的な方法は後述する。
(3)地震活動度(規模別の地震発生頻度)の評価とモデル化
地震活動度の評価とモデル化は、地域区分する方法と地域区分しない方法それぞれについて以下のとおりである。
<地域区分する方法>
- 地震活動域は、料率算定会の区分を用いる。料率算定会の地震活動域は、上部地殻内については萩原編(1991)による地震地体構造区分を、太平洋プレートおよびフィリピン海プレートについては上記の地体構造区分に加えて震央分布やプレート上面の深さなどをそれぞれ参考にして設定されたものである。
- 地震活動域は、近年の知見を踏まえて今後再検討する必要がある。
- グループ5の地震、フィリピン海プレートのグループ3+4の地震のそれぞれについて、地震活動域ごとに過去に発生した地震のデータを用いて地震の規模別発生頻度を算定する。
- 上記の結果を用いて、b 値を0.9(図3.4.4-4 参照)とした上で、マグニチュード5.0以上の地震の発生頻度を算定する(マグニチュード3.0以上の地震のデータを用いる場合には、これらの地震を対象にG-R
式を算定し、その式上でマグニチュード5.0以上の地震の発生頻度を出す。図3.4.4-5 参照。)。なお、フィリピン海プレートの地震については、この時点で算定された発生頻度は、グループ3と4の地震の合計である。
- 最大マグニチュードは、料率算定会と同様の方法により、地震活動域ごとに設定する。具体的には、陸域上部地殻内の地震活動域については別途モデル化している活断層と対応しない歴史地震の最大マグニチュード(ただし6.5
あるいは6.7の下限値を設定)を、また太平洋プレート・フィリピン海プレートの地震活動域については歴史上の最大マグニチュードと垣見・他(1994)による値の大きい方(ただし7.2の下限値を設定)をそれぞれ採用している。
- ハザード評価に用いる最小マグニチュードは、用いた地震のデータの最小マグニチュードによらず5.0とする。
- 将来の地震の発生場所は、それぞれの地震活動域内で一様とする。
- 時系列は定常ポアソン過程とする。
- 将来発生する地震の深さは、各地震活動域内で一定値とする。その値は、陸域の上部地殻内の地震については一律10km、フィリピン海プレートの地震については近年の地震のデータの震源深さの平均値とする。
- 図3.4.4-6 に、試作領域周辺の地震活動域ごとの最大マグニチュードと震源深さを示す。
<地域区分しない方法>
- グループ5の地震、フィリピン海プレートのグループ3+4の地震それぞれについて、東西、南北各0.1 度のメッシュごとに過去に発生した地震のデータを用いて地震の規模別発生頻度を算定する。
- 上記の結果を用いて、b 値を一定値(0.9)とした上で、マグニチュード5.0以上の地震の発生頻度を各メッシュについて算定し、それをガウス分布で平滑化する。この際、相関距離は25km
とする。
- 最大マグニチュードは、地域区分する方法で用いている値を参照することとし、メッシュの中心が属する地震活動域の値を用いる。
- ハザード評価に用いる最小マグニチュードは5.0 とする。
- 将来の地震の発生場所は、メッシュ内で一様ランダムとする。
- 時系列は定常ポアソン過程とする。
- 将来発生する地震の深さは、地域区分する方法で用いている値を参照することとし、当該メッシュの中心が属する地震活動域の深さを用いる。
- なお、メッシュのサイズや相関距離の設定については、今後再検討する必要がある。
D. フィリピン海プレートのグループ3とグループ4の地震の分離
グループ3,4の地震を分離する方法として、震源深さによって分類する案(例えば60km
以浅をプレート間地震、60km 以深をプレート内地震とする)も検討されている。太平洋プレートの地震に関しては、このように深さ60km
を境界として分類することも一つの案として考えられる。
一方、今回のサンプル版は、甲府盆地を中心とする領域を対象としている。この領域に対しては、太平洋プレートの地震はほとんど影響することはなく、関連するグループ3とグループ4の地震は主にフィリピン海プレートの地震となる。東海地方のフィリピン海プレートの深度は比較的浅いと考えられており、仮に60km
を境界として深さのみでグループ分けをするとほぼ全てがプレート間地震に分類されるものと推測される。しかし、平成13
年2 月23 日に浜名湖付近で発生した地震(M=4.9, h=約40km)や、同年4月3 日に静岡県中部で発生した地震(M=5.1,
h=約35km)はいずれもプレート内の地震とされており、深さによる分離では不十分の可能性がある。このため、以下の考え方に基づいてグループ3とグループ4の地震を分離することが考えられる。
- フィリピン海プレートの地震を対象に、「グループ3+グループ4」の地震の発生頻度を、地域区分する方法では地震活動域ごとに、地域区分しない方法では0.1°四方のメッシュごとに算定する(C.
の(2)(3)参照)。
- 上記とは別に、東海地方(伊豆半島の西から紀伊半島の東)のフィリピン海プレート周辺で発生する地震のデータから、メカニズムと深さとの関係を調べる。
- 震源データのメカニズムからプレート間地震数とプレート内地震数の比率を計算する。
- 有効数字1桁で求まった比率をグループ3の地震発生頻度とグループ4の地震発生頻度の比率とする。
- 最大・最小マグニチュード、および発生位置(震央位置)につては、グループ3と4で同一とする。深さについては、両者に明確な差異が認められる場合には、それを考慮して設定する。
ただし、今回のサンプル版の作成では、東海地方のフィリピン海プレートの固着率が現時点において非常に高いとされることなどを勘案し、暫定的にグループ3と4の比率を 0:1、すなわち全てがグループ4 の地震であるとしてモデル化する。
E. グループ5の地震に関する固有の事項
(1)グループ5の地震を対象としたその他のモデルについて
長期評価部会では、グループ5の地震を対象としたモデル化として、ここまでに述べてきた方法以外に、活断層のデータに基づいて評価する方法(隈元モデル)も考慮することとしている。ただし、今回のサンプル版では隈元モデルは使用せず、今後、その採否も含めて検討する。なお、隈元モデルは、以下のようなものと考えられる。
- <隈元モデルの概要>
- a)上部地殻内に0.1°四方のメッシュを作成する。
- b)活断層のデータに基づき、各活断層の最大規模の地震とその発生頻度を算定する。
- c)断層の中心が属するメッシュに、上記の規模と頻度を有する地震を割り当てる。
- d)メッシュごとに、地震の規模別発生頻度を算定し、それをGutenberg-Richterの関係でモデル化する。
- e)メッシュごとに算定された頻度を、ガウス分布で平滑化する。
F. サンプル版の試作領域周辺における地震の発生頻度の分布
サンプル版の試作領域周辺を対象として、地域区分する方法、地域区分しない方法それぞれについて、2種類の地震データに基づいて評価したマグニチュード5.0
以上の地震の発生頻度(0.1°×0.1°の領域ごとの1 年あたりの頻度)の分布を図3.4.4-7 および図3.4.4-8 に示す。
まず、地域区分する方法と地域区分しない方法による発生頻度を比較すると、前者では区分した領域内で地震の発生頻度が一様であるのに対して、後者では場所による地震発生頻度のコントラストがきわめて強くなるために、除去しきれていない余震や群発地震の影響が直接的に現れる結果となっている。
次に、用いる地震カタログの違いによる結果の差異を見ると、地域区分する方法では発生頻度に最大3
倍程度の違いが生じている。一方、地域区分しない方法では、場所ごとのコントラストが強く出るために、用いるカタログによって発生頻度に10
倍もの違いが現れるところもある。微小地震のカタログを用いた場合には、余震や群発地震の影響をより強く受けると考えられるため、これらの結果の差異は、単純に両カタログの期間による違いだけではなく、規模の範囲が異なることの影響も反映されていると考えられる。
地域区分しない方法による結果から、2つの地震カタログに共通して地震発生頻度の高い地域(橙色以上)として、グループ3+4では茨城県南西部から千葉・埼玉両県北部にかけての領域と伊豆半島から伊豆諸島にかけての領域が挙げられる。また、グループ5では神奈川県西部から山梨県東部と新潟県中部が挙げられる。逆に、カタログによって値が大きく異なる地域は、グループ3+4では愛知県の直下が、グループ5では愛知県、長野・岐阜県境付近、長野市付近、栃木・群馬県境付近、茨城県南西部から千葉県北部等が挙げられる。
G. サンプル版の作成における複数のモデルの取扱い
グループ3〜5の地震については、上記のように
- 地域区分:する/しない
- 地震カタログ:中地震/微小地震
の組み合わせで合計4 ケースが存在する。サンプル版の作成では、これら4ケースによる結果の平均値(地震動の強さごとに超過確率の算術平均をとったもの)を用いる場合を基本ケースとし、参考図用として、地域区分しない方法と微小地震を組み合わせたものを採用する。
- 参考文献
- ・Frankel, A. (1995): Mapping Seismic Hazard in the Central and Eastern
United States, Seismological Research Letters, Vol. 66, No. 4, pp. 8-21.
- ・萩原尊禮編(1991):日本列島の地震−地震工学と地震地体構造−,鹿島出版会.
- ・垣見俊弘・ほか(1994):日本列島の地震地体構造区分と最大地震規模,地球惑星科学関連学会1994
年合同大会予稿集,p.132.
- ・建設省土木研究所地震防災部振動研究室(1983):前・余震の頻度および規模に関する調査,土研資料No.1995.
- ・気象庁地震火山部(2001):気象庁マグニチュード検討委員会の検討結果,報道発表資料,平成13
年4 月23 日.
- ・損害保険料率算定会(2000):活断層と歴史地震とを考慮した地震危険度評価の研究〜地震ハザードマップの提案〜,地震保険調査研究47.
- ・宇津徳治(1982):日本付近のM6.0 以上の地震および被害地震の表:1885 年〜1980 年,地震研究所彙報,Vol. 57, pp. 401-463.
- ・宇津徳治(1985):日本付近のM6.0 以上の地震および被害地震の表:1885 年〜1980
年(訂正と追加),地震研究所彙報,Vol. 60, pp. 639-642.
|