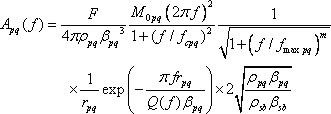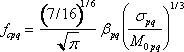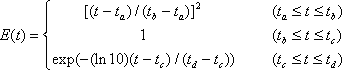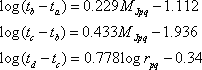付録B. 詳細法計算手法B.1 三次元有限差分法B.1.1 手法の概要 有限差分法は有限要素法とならんで解析領域全体を離散化して解く方法(領域法)の代表的なものである。具体的には、対象領域内に配置された離散化された節点(格子点)において、波動場を記述する波動方程式の変数にテイラー展開を適用し微係数を差分近似することで格子点での値に関する連立一次方程式(差分方程式)を作成し、これを逐次解いていく方法である。 B.1.2 地盤および波動伝播特性のモデル化と精度媒質の離散化における格子点(グリッド)の配置方法として、食い違い格子あるいはスタッガードグリッド(staggered grid)と呼ばれるものを用いる。これは、変位(あるいは速度)を評価する格子点と応力を評価する格子点を格子点間隔 の半分だけずらす方法である(例えば、Virieux and Madariaga, 1982)。変位勾配から歪み・応力が決まるという物理的な性質をよく表すことから自然であり、数値安定性が向上する利点がある。ただし、変位(あるいは速度)の各成分の格子点が互いに異なる点にあるため、厳密には同一点での値を求めることができない不自由さがある。図B.1-1にGraves(1996)の論文に記載されている食い違い格子の模式図を示す。図中、速度の各成分は黒印の点で計算され、応力の各成分は、その黒印の点から半グリッド だけずれた白印の点で計算される。また、媒質を規定するパラメータである密度およびラーメの定数(密度、P波速度、S波速度を与えればラーメの定数は一意に定まる)は白丸の点毎に独立に与えられる。 (2)離散化誤差と数値安定性 微分演算の差分近似は、微分点の前後での値の変化が十分に小さいことを仮定してテイラー展開を用いて誘導されるので、離散化誤差を小さくするためには格子点間隔を対象波長に対して小さく選ぶ必要がある。格子点間隔を対象波長の何分の一以下にすべきかは差分方程式の近似度(あるいは精度ともいう)によって決まる。微分法の値は近似度4(4次精度)の場合、その周囲の4つの格子点の値から定まる。三次元波動場の計算に最近よく用いられる差分法は空間に関して近似度4のものが多い(例えば、Frankel and Vidale, 1992; Graves, 1996; Pitarka, 1999)。実際の計算上の精度を確保するための格子点間隔は、空間に関して近似度4の場合、対象波長の5分の1以下にする必要がある(Levander, 1988)。それよりも短い波長の波は減衰させられる(例えば、Buell, 1991; 竹中, 1993)と同時に位相速度の変化(数値分散)が顕著になる。波動方程式を陽解法型の差分方程式に近似して解く場合の差分スキームの安定性を確保するための必要条件は、単位の時間ステップ
(3)吸収境界条件 計算機の能力に限界があることから、有限差分法でモデル化できる媒質の範囲(計算領域)は限られる。計算領域の境界面に何らの境界条件も与えないとこれらの面は剛体壁(固定端)として振る舞うため、この面に達した波は完全反射して計算領域内に戻ってきてしまう。しかし、実際の地盤にこのような壁は存在しない。この計算上の反射波を防ぐには、十分大きな計算領域を設定し、反射波が着目地点に戻ってくる前に計算を打ち切る必要がある。しかし、この方法では計算する地震波の継続時間が長ければ長いほど計算領域を大きくとらなければならなくなり、記憶容量、計算時間とも膨大になってしまう。そこで、計算領域を必要以上に大きくとらない方法として、境界面に入射した波が吸収される吸収境界条件(absorbing boundary condition)が開発された。この吸収境界条件としてはClayton and Engquist(1977)のものが有名であるが、この吸収境界条件だけでは反射波の抑止が完全ではない。そこで最近では、境界面から20あるいは30点の格子点を帯状の波動吸収領域として用い、この中では時間ステップ毎に波の振幅に指数関数を乗じ振幅を徐々に減少させる方法(Cerjan et al., 1985)が用いられている。Graves(1996)、Pitarka (1999)の有限差分法では、Clayton and Engquist(1977)の吸収境界条件とCerjan et al.(1985)の帯状の吸収領域が併用されている。 (4)地表面における応力解放条件 直交格子を基本とする有限差分法で地表面における応力解放条件を満足させ、かつ数値安定性を確保することはそう簡単ではない。有限差分法で地表面を扱う方法の一つは自由地表面での応力零の条件を陽に定式化する方法である(Zero - stress formulation)。地表面が水平な場合には場の逆対称性を利用して応力零の条件を満足するために必要な地表面上および地表面より上の空中の格子点の変位や応力の値を容易に計算できる(例えば、Levander, 1988; Graves, 1996; Pitarka, 1999)。この場合には数値的な安定性が確保され精度もよい。しかし、この方法を凹凸がある地表面に適用することは難しい。 (5) 媒質の一般的な非弾性減衰を考慮するには応力と歪みとのコンボリューションの操作が必要となるため単純な陽解法を維持できなくなり、計算に必要な記憶容量や計算時間が格段に増大する(例えば、Emmerich and Korn, 1987)。そのため、これまでの有限差分法の計算では B.1.3 震源のモデル化断層面上の滑り時間関数や破壊時刻といった運動学的パラメータを先験的に与える運動学的断層モデルの場合、有限差分法のような領域法に属する離散化手法で最も問題なのは、一つの格子点にダブルカップルを厳密に作用させるのが簡単ではないことにある。この問題点の解決法として、分布震源を用いる方法とソースボックス法の二通りがある(竹中, 1993)。前者は有限な広さを持つ複数の格子点にそれぞれ異なった向きのシングルフォースを作用させることで分布震源としてダブルカップルを近似的に表現する方法である(Aboudi, 1971)。この方法は簡便なことからよく用いられてきた(例えば、Frankel, 1993)。最近、Graves(1996)はこの方法と食い違い格子(スタッガードグリッド)との取り合わせがよいことに着目し、三次元場の食い違い格子におけるモーメントテンソルの表現式を導いている。Pitarka (1999)でもGraves(1996)と同様の方法でダブルカップルの点震源をモデル化している。 B.1.4 不等間隔格子による有限差分法本検討では、不等間隔格子を用いたPitarka (1999)の有限差分法により計算を行う。不等間隔格子の模式図を図B.1-2に示す。有限差分法による計算を行う際には、計算の対象とする媒体を直方体の格子点に離散化する。この時、計算の安定条件を満たすために、格子間隔は (B-1) 式と次の条件を満たす必要がある。
ここで、 B.2 統計的グリーン関数法B.2.1 地震基盤における統計的グリーン関数の作成 地震基盤における統計的グリーン関数は、佐藤ほか(1994a, 1994b)が仙台地域で観測された主に海溝型地震の記録から推定したパラメータを用いたスペクトルモデルと経時特性モデルを用いて、Boore(1983)と同様の手法で作成した。
ここに、
で表される値とした。(B-2)式は、佐藤ほか(1994b) の推定値であるが、最近の研究では、0.8Hz前後以下で
ここで、
ここに、
気象庁マグニチュード B.2.2 工学的基盤上面での統計的グリーン関数の作成各計算ポイント直下の三次元地盤モデルから、各計算ポイントでの1次元地盤モデルを作成し、B.2.1において作成された地震基盤における統計的グリーン関数を入射波として、S波の一次元重複反射理論により、工学的基盤上面での統計的グリーン関数を計算する。 B.2.3 工学的基盤上面における統計的グリーン関数を用いた波形合成B.2.2で作成された工学的基盤上面における統計的グリーン関数を用いて、壇・佐藤(1998)の断層の非一様すべり破壊を考慮した半経験的波形合成法に従い、波形合成を行う。この際、大地震の要素断層のすべり量と応力降下量が再現されるように、震源スペクトルの補正を行った。このようにして算定された大地震の要素断層の波形を断層面全体の破壊過程を考慮して合成を行う。 B.3 ハイブリッド合成法 ハイブリッド合成法は、短周期領域と長周期領域においてそれぞれ求めておいた2つの計算結果を合成して広帯域地震動を評価する方法である(例えば、川瀬・松島,
1998; 佐藤ほか, 1998 ; 入倉・釜江, 1999)。この手法の特徴は、地盤や断層の不均質性の影響を受けにくく波動モデルで説明可能な長周期地震動を物理モデルに基づいて理論的に計算し、逆に地盤や断層の不均質性の影響を受け易く統計的にしか説明できない、もしくは理論的な計算効率が悪い短周期地震動を統計的に計算することである。ここでは、短周期側は統計的グリーン関数法、長周期側は三次元有限差分法により求めた工学的基盤上面での時刻歴波形を用いる。合成は、ある周期(接続周期)を中心とするコサイン型フィルタの組み合わせによるマッチングフィルタを用いて時刻歴波形をフィルタ処理し、時刻歴で重ね合わせて行う。両領域を接続する周期は、地下構造データや振動特性、差分法計算に用いる計算機の能力を考慮して決定する。短周期成分はハイパスフィルタ処理を、長周期域成分はローパスフィルタ処理を行った後、両者を重ね合わせて接続する。両フィルタとも接続周期
|