�@4.2.2�@�����I�k�������̐ݒ�
�@�����I�k�������̐ݒ�Ɋւ��āA�P�j �` �R�j�̍��ڂɂ��Ĉȉ��̂悤�Ɍ��������B
�@�P�j �k���f�w���f���̈ʒu�E�`��
�@�k���f�w���f���̈ʒu�ɂ��ẮA�u�����]���v�ɂ�銈�f�w�ʒu�}�i�}4.1�Q�Ɓj�ɐݒ肵���B�����ɂ��ẮA��{�I�Ɂu�����]���v�ɂ�������A�R��f�w�ю啔�̖k�����i������51km�j�A����ё��J�f�w�i������13km�j�ɂ��ẮA�k���f�w���f���̍쐬�̓s����A���ꂼ��52km�A�����14km�Ƃ����B���f���P�ɂ��ẮA�k���f�w������ł��邽�߁A�S�̂łP�̃Z�O�����g�Ƃ���ꍇ�i�b�`�r�d�P�|�P�j�̑��ɁA�Z�O�����g���Q�ɕ����A�u�����]���v���Q�l�ɁA�匴�f�w�E�y���f�w�E���x�f�w���P�Z�O�����g�i�ȉ��A��P�Z�O�����g�j�A�쓌�����P�Z�O�����g�i�ȉ��A��Q�Z�O�����g�j�Ƃ���ꍇ���z�肵���i�b�`�r�d�P�|�Q�j�B�Z�O�����g�����ꍇ�̓������k�����f���̐ݒ���@�ɂ��Ă̓��V�s�ɏ]�����B�������A���f�w�����ɂ����āA�Z�O�����g����O���[�v���Ɋւ��ẮA�܂��c�_�̓r��ɂ���A����̌����ۑ�ƂȂ��Ă���B
�@�Q�j �n�k�����w�̐[��
�@�n�k�����w�̐[���ɂ��ẮA���f���T�i�ߊ�R�f�w�сj�ȊO�̃��f���ł́A���̏���A�������u�����]���v������n�k�̐[�����z(�}4.4�Q��)���Q�l�ɁA���ꂼ��Rkm�A21km�ɐݒ肵���B���f���T�ɂ��ẮA�[����ݒ肷�邾���̏\���Ȕ����n�k�L�^�������Ă��Ȃ����Ƃ���A���̒f�w�тƓ��l�ɁA�Rkm�A21km�ɐݒ肵���B
�@�R�j �k���f�w���f���̌X��
�@�k���f�w���f���̌X�Ίp�́A���f���T�i�ߊ�R�f�w�сj�ȊO�̃��f���ɂ��ẮA�u�����]���v�ɂ��A�u�n���[���ɂ�����f�w�ʂ̌X���n�\�Ɠ��l�ł���Ƃ���Βf�w�ʂ͂قڐ����Ɛ��肳��邱�Ɓv����90���Ƃ����B���f���T�i�ߊ�R�f�w�сj�ɂ��ẮA�u�����]���v�ł͌X�͕s���Ƃ���Ă��邪�A�k�����쑤�ɑ��đ��ΓI�ɗ��N����f�w�ł���Ƃ̋L�ڂ��Q�l�ɁA�k�����N�̋t�f�w��z�肵�A�X�Ίp�̓��V�s�ɏ]��45���Ƃ����B
�@�S�j �k���f�w���f���̖ʐ� 
�@�܂��A��L�̒n�k�����w�̏��������[���A����ьX�Ίp����k���f�w���f���̕����Z�肵��[(4-1)���Q��]�B������A���f���T�i�ߊ�R�f�w�сj�������e�k���f�w���f���̕���18km�ƂȂ�B
�@���f���T�i�ߊ�R�f�w�сj�ɂ��ẮA�k���f�w���f���̌X�Ίp��45���Ƃ��Ă��邱�Ƃ���A�n�k�����w�̐[���̏㉺���l���l�����āA����26km�Ƃ����B
�@���ɁA�e�k���f�w���f���̖ʐς��A�e�k���f�w���f���̕��ƒ�������Z�o�����B
�@�T�j �n�k���[�����g 
�@�k���f�w���f���̒n�k���[�����g�ɂ��ẮA���V�s�ɂ����Đk���f�w�̖ʐς�291  �ȏ�̏ꍇ�ɓK�p����Ƃ��������n�k�̒n�k���[�����g �ȏ�̏ꍇ�ɓK�p����Ƃ��������n�k�̒n�k���[�����g  �ƒf�w�ʐ� �ƒf�w�ʐ�  �Ƃ̊W�Ɋ�Â��Đ��肵��[(4-3)���Q��] �B�n�k���[�����g �Ƃ̊W�Ɋ�Â��Đ��肵��[(4-3)���Q��] �B�n�k���[�����g  �ƒf�w�ʐςr�̊W�ɂ��ĉߋ��̒n�k�̉�͌��ʂ��܂Ƃ߂��}�ɁA����̐ݒ�l���v���b�g�����}4.5(��)�Ɏ����B �ƒf�w�ʐςr�̊W�ɂ��ĉߋ��̒n�k�̉�͌��ʂ��܂Ƃ߂��}�ɁA����̐ݒ�l���v���b�g�����}4.5(��)�Ɏ����B
�@�܂��A�Z�O�����g�����b�`�r�d�P�|�Q�ɂ��ẮA�k���f�w�S�̂̒n�k���[�����g��(4-3)�����琄�肵�A�����(4-4)���ɏ]���Ċe�Z�O�����g�̒f�w�ʐς�1.5��ɔ�Ⴗ��悤�ɔz�������B�Ȃ��A�ߔN�̌����ɂ����āA�ŋߔ������������̃Z�O�����g�̔j�����n�k�̃f�[�^�̉�͂���A�f�w�Z�O�����g���A�����Ēn�k���N�����Ă��X�̃Z�O�����g�̕ψʗʂ͈��Ƃ���J�X�P�[�h�n�k���f���̓K�����ǂ��Ƃ̕�����i�Ⴆ�C���c�C2004�G���c�C2004�j�B�������A�Z�O�����g�������s�����ꍇ�̃X�P�[�����O����������k�����f���̐ݒ���@�ɂ��ẮA�����i�K�ɂ��邽�߁A����̌����ΏۂƂ͂��Ȃ������B
�@�U�j ���ς��ׂ�� 
�@�k���f�w���f���S�́A�y�ъe�Z�O�����g�i�b�`�r�d�P�|�Q�j�̕��ς��ׂ��  �́A�z��k����̕��ϓI�ȍ����� �́A�z��k����̕��ϓI�ȍ�����  �A�f�w�ʐ� �A�f�w�ʐ�  �A����ѕ��ς��ׂ�� �A����ѕ��ς��ׂ��  �ƒn�k���[�����g �ƒn�k���[�����g  �Ƃ̊W����p���Đ��肵��[(4-5)���Q��]�B �Ƃ̊W����p���Đ��肵��[(4-5)���Q��]�B
�@4.2.3�@�����I�k�������̐ݒ�
�@�����I�k�������̐ݒ�Ɋւ��� �P�j �` �V�j�̍��ڂňȉ��̂悤�Ɍ��������B
�@�P�j �A�X�y���e�B�̐�
�@�A�X�y���e�B�̌��́A�o����A�P�n�k�ɂ�����2.6�ŁA�P�Z�O�����g�ɂ��P�`�Q�Ƃ���Ă���[4.2.1�Q��]�B�{�����ł́A�A�X�y���e�B�̐����A�k���f�w������ł��郂�f���P�ɂ��Ă͂R�i�b�`�r�d�P�|�Q�̏ꍇ�́A��P�Z�O�����g�ɂQ�A��Q�Z�O�����g�ɂP�j�A�k���f�w�̖ʐς���r�I�傫�����f���Q�A�S�ɂ��Ă͂Q�A���̑��̃��f���͂P�Ƃ����B�}4.6 �` 4.8�ɐݒ�f�w���f���������B
�@�Q�j �A�X�y���e�B�̑��ʐ� 
�@�A�X�y���e�B�̑��ʐς́A�Z�����̈�ɂ���������x�k���X�y�N�g���̃��x���i�ȉ��A�Z�������x���Ƃ����j�ƊW�����邱�Ƃ���A�ȉ��̎菇�ŎZ�肵���B
- �d�ق� (2001)�ɂ��Z�������x���ƒn�k���[�����g�Ƃ̌o����[(4-6)���Q��]��p���āA�n�k���[�����g����Z�������x�����Z�肵���i�}4.5(��)�Q�Ɓj�B
- ��L�ŎZ�肵���Z�������x������A�X�I�ɓ������a
 �̉~�`�̃A�X�y���e�B�������Ƃ����l��������ɂ��āA�A�X�y���e�B�̑��ʐ� �̉~�`�̃A�X�y���e�B�������Ƃ����l��������ɂ��āA�A�X�y���e�B�̑��ʐ�  �����߂�[(4-7) �` (4-9)���Q��]�B �����߂�[(4-7) �` (4-9)���Q��]�B
�@�ȏ�̎菇�ɏ]���A�A�X�y���e�B�̑��ʐς��Z�肵�����ʁA�k���f�w�S�̖̂ʐςɑ���A�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦�́A���f���P�ł͂b�`�r�d�P�|�P�A�b�`�r�d�P�|�Q�Ŗ�41���A���f���Q�Ŗ�31���A���f���R�Ŗ�21���A���f���S�Ŗ�28���C���f���T�Ŗ�29���ƂȂ����B����܂ł̌������ʂł́A�A�X�y���e�B�̑��ʐς��k���f�w�S�̖̂ʐςƔ��W�ɂ��邱�Ƃ��o���I�ɒm���Ă���A�A�X�y���e�B�̒�`���������ƂɈقȂ���̂́A�����n�k�ɂ��A�X�y���e�B�̑��ʐς̐�߂銄���͑S�f�w�ʐς̕���22%(Somerville et al., 1999)�A15%�`27%(�{���ق��C2001)�A����37%�i�Έ�ق��C2000�j�Ƃ��������ʂ������Ă���B����z�肵���k���f�w���f���ɂ�����A�X�y���e�B�̑��ʐς́A���f���P�̂b�`�r�d�P�|�P�A�b�`�r�d�P�|�Q�����������͈͓̔��ɂ���B�Ȃ��A�b�`�r�d�P�|�Q�ł́A�e�A�X�y���e�B�̖ʐς͂b�`�r�d�P�|�P�ƈقȂ�i�\4.1�Q�Ɓj���A�e�Z�O�����g�ɂ�����f�w�S�̖̂ʐςƃA�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦�́A���V�s�ɏ]���ĒZ�������x������Z�肵�Ă��邽�߁A�b�`�r�d�P�|�P�Ɠ����ɂȂ�B
�@�k���f�w�̒������k���f�w�̕��ɔ�ׂď\���ɑ傫������Ȓf�w�ɑ��āA�~�`�j��ʂ����肷�邱�Ƃ͕K�������K���ł͂Ȃ����Ƃ��w�E����Ă���B���V�s�ł́A�����I�k�������ł���n�k���[�����g
 ���A�~�`�j��ʂ����肵�Ă��Ȃ�(4-3)�����琄�肵�Ă��邪�A�����I�k�������ł���A�X�y���e�B�̑��ʐς̐���ɂ́A�~�`�j��ʂ����肵���X�P�[�����O�����瓱�o����� (4-6) �` (4-9) ����K�p���Ă���B���̂悤�ȕ��@�ł́A���ʓI�ɐk���f�w�S�̖̂ʐς��傫���Ȃ�قǁA�����̒����E�������ʂɔ�r���ĉߑ�]���ƂȂ�X���ƂȂ邽�߁A�����I�k�������ɂ��Ă��~�`�j��ʂ����肵�Ȃ��X�P�[�����O����K�p����K�v������B�������A����Ȓf�w�̃A�X�y���e�B�Ɋւ���X�P�[�����O���ɂ��ẮA���̃f�[�^�����Ȃ����Ƃ���A�������̌����ۑ�ƂȂ��Ă���
�����ŁA�����ł̓��f���P�ɑ��鎎�s�b�`�r�d�Ƃ��āA(4-6) �` (4-9)����p�����A���q�E�O�� �i2001�j�ɂ��k���f�w�S�̖̂ʐςɑ���A�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦�A��22%��K�p�����ꍇ�i�b�`�r�d�P�|�R�A�b�`�r�d�P�|�S�j�̋��k���\�����s���A���̉e���ɂ��Č��������B ���A�~�`�j��ʂ����肵�Ă��Ȃ�(4-3)�����琄�肵�Ă��邪�A�����I�k�������ł���A�X�y���e�B�̑��ʐς̐���ɂ́A�~�`�j��ʂ����肵���X�P�[�����O�����瓱�o����� (4-6) �` (4-9) ����K�p���Ă���B���̂悤�ȕ��@�ł́A���ʓI�ɐk���f�w�S�̖̂ʐς��傫���Ȃ�قǁA�����̒����E�������ʂɔ�r���ĉߑ�]���ƂȂ�X���ƂȂ邽�߁A�����I�k�������ɂ��Ă��~�`�j��ʂ����肵�Ȃ��X�P�[�����O����K�p����K�v������B�������A����Ȓf�w�̃A�X�y���e�B�Ɋւ���X�P�[�����O���ɂ��ẮA���̃f�[�^�����Ȃ����Ƃ���A�������̌����ۑ�ƂȂ��Ă���
�����ŁA�����ł̓��f���P�ɑ��鎎�s�b�`�r�d�Ƃ��āA(4-6) �` (4-9)����p�����A���q�E�O�� �i2001�j�ɂ��k���f�w�S�̖̂ʐςɑ���A�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦�A��22%��K�p�����ꍇ�i�b�`�r�d�P�|�R�A�b�`�r�d�P�|�S�j�̋��k���\�����s���A���̉e���ɂ��Č��������B
�@�e�A�X�y���e�B�Ԃ̖ʐϔ�ɂ��ẮA�R�̃A�X�y���e�B��ݒ肷�郂�f���P�i�b�`�r�d�P�|�Q�������j�ɑ��ẮA�Έ�ق� (2000) ���Q�l�ɂQ:�P:�P�Ƃ����B�Q�̃A�X�y���e�B��ݒ肷�郂�f���P�̂b�`�r�d�P�|�Q�A���f���Q�A����у��f���S�ɂ��ẮA�Έ�ق� (2000) ���Q�l�ɂQ:�P�Ƃ����B
�@�R�j �A�X�y���e�B�̈ʒu
�@�u�����]���v�ɂ��A�匴�f�w�A���i�b�f�w�ł́A���������̕��ϓI�Ȃ���̑��x����r�I�傫���Ɛ��肳��Ă���B���������x�f�w�ł́A�㉺�����̕��ϓI�Ȃ���̑��x����A����������r�I�����Ɛ��肳��Ă���B
�@�����̒������ʂ��Q�l�ɁA���f���P�ɂ��ẮA�匴�f�w�ɑΉ�����f�w�іk�����ɑ傫���A�X�y���e�B(��P�A�X�y���e�B)���A���x�f�w�ɑΉ�����f�w�ђ������Ɣ��i�b�f�w�ɑΉ�����f�w�ѓ쓌���ɓ��K�͂̏������A�X�y���e�B�i��Q�A��R�A�X�y���e�B�j��z�u�����B���f���Q�ɂ��ẮA�匴�f�w�ɑΉ�����f�w�іk�����ɑ傫���A�X�y���e�B(��P�A�X�y���e�B)���A��⓻�f�w�̖k���[���ɏ������A�X�y���e�B(��Q�A�X�y���e�B)��z�u�����B���f���R�ɂ��ẮA���i�b�f�w�ɑΉ�����f�w�ђ������ɃA�X�y���e�B��z�u�����B���f���S�ɂ��ẮA���f���R�Ɠ��l�ɁA�R��f�w�ю啔�̓쓌���̒������ɑ傫���A�X�y���e�B(��P�A�X�y���e�B)���A���J�f�w�̑��J�t�߂̃g�����`�������ʓ����Q�l�ɁA���J�f�w�̖k���[���ɏ������A�X�y���e�B(��Q�A�X�y���e�B)��z�u�����B���f���T�ɂ��ẮA�A�X�y���e�B�̈ʒu��ݒ肷�邽�߂̏��ɖR�������Ƃ���A���V�s�ɏ]���āA���ϓI�Ȃb�`�r�d�Ƃ��Ēf�w�ђ������ɃA�X�y���e�B��z�u�����B�A�X�y���e�B��z�u�����[���ɂ��ẮA�ǂ̃��f���ɂ��Ă��f�w�����Ƃ����B
�@�Ȃ��A�b�`�r�d�P�|�R�A�b�`�r�d�P�|�S�ɂ��ẮA�A�X�y���e�B�̕��ʓI�Ȉʒu�́A�b�`�r�d�P�|�P�Őݒ肵���ʒu�Ɛ��[������v�����邱�ƂƂ��A�[���͒f�w�������Ƃ����B
�@�S�j �A�X�y���e�B�E�w�i�̈�̕��ς��ׂ��
�@�A�X�y���e�B�S�̂̕��ς��ׂ�ʂ́A�ŋ߂̓����n�k�̉�͌��ʂ��������ʁiSomerville et al., 1999�j����ɐk���f�w�S�̂̕��ς��ׂ�ʂ̂Q�{�Ƃ��A�e�A�X�y���e�B�̂��ׂ�ʁA����єw�i�̈�̂��ׂ�ʂ��Z�肵�� [(4-10) �` (4-14)���Q��]�B
�@���̌��ʁA�A�X�y���e�B�̕��ς��ׂ�ʂ́A���f���P�A�Q�A�R�A�S�A����у��f���T�ŁA���ꂼ���5.0���A��3.2���A��1.9���A��2.7���A����і�2.6���ƂȂ�B�u�����]���v�ƒ��ڔ�r���ł��Ȃ����f���P�A�S�ȊO�́A���f���Q�A�R�A����у��f���T�ɑ���u�����]���v�ɂ��1��̂���̗ʂ́A�R��f�w�ю啔�̖k�����Ŗ�Q���A�R��f�w�ю啔�̓쓌���łQ�����x�i�ȏ�A�������ꐬ���j�A����ѓߊ�R�f�w�тŖ�Q�|�R���i�㉺�����j�ł���A������̃��f���ɂ��Ă����҂͒��a�I�ł���B�܂��A�Q�l�܂łɁA���f���P�A���f���S�ɂ��āA�f�w�������琄�肳���P��̊����ɔ����ψʗʂ��r����ƁA���f���P�i�f�w����80km�j��6.4���A���f���S�i�f�w����44km�j��3.5���ƂȂ�A�������T�˒��a�I�Ȍ��ʂƂȂ��Ă���B�Ȃ��A�n�\�ł̂P��̂���̗ʂƋ��k���C���o�[�W�����Ő��肳��Ă��镽�ς��ׂ�ʂƂ��ǂ̂悤�ȊW�ɂ��邩�\���Ɍ�����Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ��K�v�ł���B
�@�T�j �A�X�y���e�B�̉��͍~���ʁE�������́A����єw�i�̈�̎�������
�@�A�X�y���e�B�̉��͍~���ʁE�������́A����єw�i�̈�̎������͂́A�A�X�y���e�B�̖ʐς���P�̉~�`�̃A�X�y���e�B�����݂���ƌ��Ȃ��ĎZ�肵��[(4-15) �` (4-17)���Q��]�B
�@�������A(4-6) �` (4-9)����p�����ɁA�k���f�w�S�̖̂ʐςɑ���A�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦���22%�Ƃ��ĎZ�o�����b�`�r�d�P�|�R�ł́A�A�X�y���e�B�̉��͍~���ʂ�24.2MPa�ŁA�b�`�r�d�P�|�P�̖�1.9�{�ƂȂ����B����́A(4-6) �` (4-9)����p���ĒZ�������x������Z�o�����A�X�y���e�B�̑��ʐρi��593  �j�Ɛk���f�w�S�̖̂ʐς̖�22%�Ƃ��ĎZ�o�����A�X�y���e�B�̑��ʐρi��310 �j�Ɛk���f�w�S�̖̂ʐς̖�22%�Ƃ��ĎZ�o�����A�X�y���e�B�̑��ʐρi��310  �j�̔䗦�ɑ�������B �j�̔䗦�ɑ�������B
�@Madariaga (1979)�ɂ��A�A�X�y���e�B�̉��͍~����  �Ɛk���f�w�S�̂̕��ω��͍~���� �Ɛk���f�w�S�̂̕��ω��͍~����  �̊W�́A���̗��_���ŗ^������B �̊W�́A���̗��_���ŗ^������B
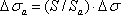 |
(4-23) |
 �F�k���f�w�S�̖̂ʐ� �F�k���f�w�S�̖̂ʐ� |
 �F�A�X�y���e�B�̑��ʐ� �F�A�X�y���e�B�̑��ʐ� |
�@(4-15)���́A�~�`�j��ʂ�����ł���悤�ȋK�͂̐k���f�w�ɑ��ẮA(4-1)���Ɠ����ł��邽�߁A(4-6) �` (4-9)����p���ĒZ�������x������A�X�y���e�B�̑��ʐς��Z�肵�A����Ƀ��V�s(4-15)����p���ăA�X�y���e�B�̉��͍~����  �𐄒�ł���B�������A���f���P�̂悤�ɁA�k���f�w�̒������k���f�w�̕��ɔ�ׂď\���ɑ傫������Ȓf�w�ɑ��ẮA�~�`�j��ʂ����肷�邱�Ƃ��K���ł͂Ȃ����߁A���V�s(4-6) �` (4-9)����p�����ꍇ�ɂ́A�k���f�w�S�̖̂ʐς��傫���Ȃ�قǁA�A�X�y���e�B�̑��ʐς������̒����E�������ʂɔ�r���ĉߑ�ƂȂ�X��������i�b�`�r�d�P�|�P�j�B�܂��A�b�`�r�d�P�|�R�̂悤�ɁA�k���f�w�S�̖̂ʐςɑ���A�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦��ݒ肵�A�~�`�j��ʂ����肵��(4-15)������A�X�y���e�B�̉��͍~���� �𐄒�ł���B�������A���f���P�̂悤�ɁA�k���f�w�̒������k���f�w�̕��ɔ�ׂď\���ɑ傫������Ȓf�w�ɑ��ẮA�~�`�j��ʂ����肷�邱�Ƃ��K���ł͂Ȃ����߁A���V�s(4-6) �` (4-9)����p�����ꍇ�ɂ́A�k���f�w�S�̖̂ʐς��傫���Ȃ�قǁA�A�X�y���e�B�̑��ʐς������̒����E�������ʂɔ�r���ĉߑ�ƂȂ�X��������i�b�`�r�d�P�|�P�j�B�܂��A�b�`�r�d�P�|�R�̂悤�ɁA�k���f�w�S�̖̂ʐςɑ���A�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦��ݒ肵�A�~�`�j��ʂ����肵��(4-15)������A�X�y���e�B�̉��͍~����  �𐄒肵���ꍇ�ɂ́A�n�k���[�����g���傫���Ȃ�قǁA �𐄒肵���ꍇ�ɂ́A�n�k���[�����g���傫���Ȃ�قǁA �������̒����E�������ʂɔ�r���ĉߑ�ƂȂ�X���ɂ���B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́AMadariaga (1979) �ɂ��A�k���f�w�̔����I�k�������Ɋւ���X�P�[�����O���Ƃ��Ĉ�ʓI�ɐ������闝�_���i(4-23)���j��p���āA�k���f�w�S�̖̂ʐςɑ���A�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦�̋t���iS/Sa�j�Ɛk���f�w�S�̂̕��ω��͍~���� �������̒����E�������ʂɔ�r���ĉߑ�ƂȂ�X���ɂ���B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́AMadariaga (1979) �ɂ��A�k���f�w�̔����I�k�������Ɋւ���X�P�[�����O���Ƃ��Ĉ�ʓI�ɐ������闝�_���i(4-23)���j��p���āA�k���f�w�S�̖̂ʐςɑ���A�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦�̋t���iS/Sa�j�Ɛk���f�w�S�̂̕��ω��͍~����  ���� ����  �𐄒肷�邱�Ƃ��ł���B����Ȓf�w�ɑ��� �𐄒肷�邱�Ƃ��ł���B����Ȓf�w�ɑ���  �ɂ��ẮA������������Ȃ��A�ėp���̂��鐔�l��ݒ肷�邱�Ƃ͓�����A�����ł͎��s�I�ɁA�k���f�w�S�̖̂ʐςɑ���A�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦���22���Ƃ�����ŁAFujii and Matsu'ura (2000) ������ȉ�����f�w�̋����I�k�������ɑ���W�����瓱�o����3.1MPa ��p�����ꍇ�ɂ��Č������邱�ƂƂ���(�b�`�r�d�P�|�S)�B���̒l��p����ƁA�A�X�y���e�B�̉��͍~���� �ɂ��ẮA������������Ȃ��A�ėp���̂��鐔�l��ݒ肷�邱�Ƃ͓�����A�����ł͎��s�I�ɁA�k���f�w�S�̖̂ʐςɑ���A�X�y���e�B�̑��ʐς̔䗦���22���Ƃ�����ŁAFujii and Matsu'ura (2000) ������ȉ�����f�w�̋����I�k�������ɑ���W�����瓱�o����3.1MPa ��p�����ꍇ�ɂ��Č������邱�ƂƂ���(�b�`�r�d�P�|�S)�B���̒l��p����ƁA�A�X�y���e�B�̉��͍~����
 �́A��14.4MPa�ƂȂ�A�b�`�r�d�P�|�P�i��12.6MPa�j�Ɠ����x�ɂȂ�B�������A3.1MPa�́A����ȉ�����f�w�̋����I�k�������Ɋւ���o�����Ƃ��āA�n�k�����w�̍�������40GPa�i���f���P�͖�32GPa�j�A�f�w����15km�i���f���P��18km�j�Ƃ��铙�̂������̏������œ��o���ꂽ�l�ł���A���̓K�p�͈͓��ɂ��Ă͌����ۑ�ƂȂ��Ă���i���q, 2004�j�B �́A��14.4MPa�ƂȂ�A�b�`�r�d�P�|�P�i��12.6MPa�j�Ɠ����x�ɂȂ�B�������A3.1MPa�́A����ȉ�����f�w�̋����I�k�������Ɋւ���o�����Ƃ��āA�n�k�����w�̍�������40GPa�i���f���P�͖�32GPa�j�A�f�w����15km�i���f���P��18km�j�Ƃ��铙�̂������̏������œ��o���ꂽ�l�ł���A���̓K�p�͈͓��ɂ��Ă͌����ۑ�ƂȂ��Ă���i���q, 2004�j�B
�@�����̂b�`�r�d�̒n�k���[�����g  �ƒf�w�ʐςr�̊W�ɂ����}4.5(��) �ɁA�܂��A�Z�������x��A�ƒn�k���[�����g �ƒf�w�ʐςr�̊W�ɂ����}4.5(��) �ɁA�܂��A�Z�������x��A�ƒn�k���[�����g  �Ƃ̊W�ɂ��āA�}4.5(��)�Ƀv���b�g���Ď����B�b�`�r�d�P�|�R�ɂ��ẮA�}4.5(��)����A�d�ق� (2001) ���܂Ƃ߂��f�[�^�̂���͈͓̔��ł͂��邪�A�Z�������x�������傫�ڂɐ��肳��Ă���B����A�b�`�r�d�P�|�S�̒Z�������x���́A�A�X�y���e�B�̉��͍~���ʂ����債������ŃA�X�y���e�B�̑��ʐς��������Ȃ������߁A�d�ق� (2001)�ɂ��o���� [(4-6)���Q��] �ɔ�r���Ď�������B �Ƃ̊W�ɂ��āA�}4.5(��)�Ƀv���b�g���Ď����B�b�`�r�d�P�|�R�ɂ��ẮA�}4.5(��)����A�d�ق� (2001) ���܂Ƃ߂��f�[�^�̂���͈͓̔��ł͂��邪�A�Z�������x�������傫�ڂɐ��肳��Ă���B����A�b�`�r�d�P�|�S�̒Z�������x���́A�A�X�y���e�B�̉��͍~���ʂ����債������ŃA�X�y���e�B�̑��ʐς��������Ȃ������߁A�d�ق� (2001)�ɂ��o���� [(4-6)���Q��] �ɔ�r���Ď�������B
�@�U�j 
�@ �ɂ��ẮA����𐄒肷�邽�߂̏�Ȃ����߁A�n�k�����ψ���k���]������ �i2001�j �̌������ʂɊ�Â���UHz�ɐݒ肵���B �ɂ��ẮA����𐄒肷�邽�߂̏�Ȃ����߁A�n�k�����ψ���k���]������ �i2001�j �̌������ʂɊ�Â���UHz�ɐݒ肵���B
�@�V�j ���ׂ葬�x���Ԋ�
�@�����E�{�� (2000) �̋ߎ�����p����[ (4-18) �` (4-21)���Q��]�B
�@4.2.4�@���̑��̐k������
�@�P�j �j��J�n�_�̈ʒu
�@�j��J�n�_�ɂ��ẮA���̈ʒu����肷�邾���̏�����Ă��Ȃ��B�����ŁA�b�`�r�d�P�ł́A�n�Ց������ʂɉ����ăf�B���N�e�B�r�e�B���� �ɂ��A���˓��C���ݒn��ŗh�ꂪ�傫���Ȃ�Ɨ\�z�����b�`�r�d�Ƃ��āA��P�A�X�y���e�B�̖k���[�̉����ɐݒ肵���i�}4.6�j�B�b�`�r�d�Q�́A�j��J�n�_�̈Ⴂ���]�����ʂɗ^����e���ׂ邽�߂ɁA��P�A�X�y���e�B�̖k���[�̉����i�b�`�r�d�Q�|�P�j�Ƃ���ꍇ�ƁA��Q�A�X�y���e�B�̓쓌�[�̉����i�b�`�r�d�Q�|�Q�j�Ƃ���ꍇ�̂Q�b�`�r�d��z�肵���i�}4.7�j�B�b�`�r�d�R�ɂ��ẮA�b�`�r�d�P�Ɠ��l�̊ϓ_����A�A�X�y���e�B�̖k���[�̉����ɐݒ肵���i�}4.7�j�B�b�`�r�d�S�ɂ��ẮA�ߋ��ɂQ�̒f�w�i�сj�������Ɋ��������\��������i���Ɍ�, 2001�j���Ƃ���A��Q�A�X�y���e�B�̖k���[�����Ƃ����i�}4.8�j�B�b�`�r�d�T�ɂ��ẮA�A�X�y���e�B�̒������[�Ƃ����i�}4.8�j�B
�@�Q�j �j��`�d�l��
�@�j��́A�o���I�ɔj��J�n�_������ˏ�i�T�˓��S�~��j�ɐi�s������̂Ƃ����B
�@�R�j �j��`�d���x
�@���ϔj��`�d���x�́A�n�k�����w�̂r�g���x�Ƃ̊W(Geller, 1976)���狁�߂�[(4-22)���Q��]�B
|